運命のいたずら(下)
アポロに負けた旧ソ連が、どうしても譲れなかったもの…人類初の長期宇宙滞在型ステーション「サリュート」の第1号機が打ち上げられ、いま正に、それに向けて最初のクルーが出発しようとしていた。レオーノフ、クバソフ及びコローディンの3人…しかし、打ち上げの数日前、クバソフの肺に異常が見つかり、クルー丸ごと交代を宣告されてしまった。これが彼らに与えたショックは大きく、特にコローディンは、現場主任のミーシンを罵倒してしまう程だった。
結局、最終的にサリュートへ向かうことになったのは、ドブロボルスキー、ボルコフ並びにパチャーエフの3人となった。そもそも彼らは、候補としてはバックアップのバックアップというポジションで、実際に飛行することになろうとは、全く頭になかったと言われる。事実、ドブロボルスキーが訓練を開始したのは僅か4ヶ月前であった程だ。
それ故、この直前の決定は、とまどいはあったものの、嬉しくもあったに違いない。特に、ドブロボルスキーとパチャーエフにとっては、初めて宇宙を飛ぶのでもあった。彼らにとっては、ラッキーこの上無いことだったに違いない。
だがしかし、宇宙船どうしのドッキングや、ランデブー(至近距離併走飛行)は誰も未経験だった。ボルコフはソユーズ7号での飛行経験があるものの、それらのミッションは経験していなかった…経験が少ない上に、訓練も充分とは言えない3人には、期待と責任がのしかかる。ソ連初の宇宙ステーション滞在は、重いプレッシャーでもあった。
◇
1971年6月6日モスクワ時間・午前4時55分、バイコヌール宇宙基地より3人を乗せたソユーズ11号が、多くの関係者に見送られる中、飛び立った。船長はドブロボルスキー。6分後には地球を周回する軌道に達し、サリュートへの接近が開始された。
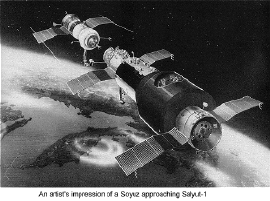 翌日、サリュートまであと7キロというところで、自動誘導装置をオンにした。こいつは過去のミッションや、開発段階で多くのトラブルを抱えたクセモノだったが、今回はなんの問題もなく作動した。サリュートが肉眼で確認される距離まで迫ると、ドブロボルスキーは手動制御に切り替え、ソロリソロリと船を近づけていった。その時、ソユーズとサリュートの距離は約100メートル、高度約300キロ。(右・想像図)
翌日、サリュートまであと7キロというところで、自動誘導装置をオンにした。こいつは過去のミッションや、開発段階で多くのトラブルを抱えたクセモノだったが、今回はなんの問題もなく作動した。サリュートが肉眼で確認される距離まで迫ると、ドブロボルスキーは手動制御に切り替え、ソロリソロリと船を近づけていった。その時、ソユーズとサリュートの距離は約100メートル、高度約300キロ。(右・想像図)
ドブロボルスキー船長はゆっくりと近づけ、モスクワ時間午前7時49分、両者は完全にドッキングした。ソユーズ10号の時(前号参照)と違い、完全なハードドッキングが達成されている。打ち上げからちょうど丸1日が経過していた。
彼らはハッチを開け、サリュートの中へ入り始めた。この、記念すべき第一歩を踏み出したのは、パチャーエフだった。いや、無重力では、「足で踏み入る」というより、スルーッと「泳ぎ入る」と言った方が妥当だろう。彼は入るやいなや、空調設備の電源を入れた。その後にボルコフが続き、最後にドブロボルスキーが入った。
しかし、3人がサリュートへ入って真っ先に感じたのは、妙な臭い…何かが焦げる臭いで、強いものだった。空調でそれを取り除くには約20時間もかかってしまい、サリュートでの第一夜は、念のためソユーズで眠ることになった。
スタートから不調はあったものの、歴史的な「宇宙ステーション」での活動が、ここに始まった。翌8日、ソ連政府は世界に、大々的に報道、いや、宣伝した。
「世界初の宇宙ステーション、始動!」
◇
サリュートでは、科学実験や天体観測といった、数多くのミッションが予定されていた。彼らの滞在予定は約4週間であったが、その間は正に、多忙を極めるものであった。内容としては、単に船内の状態を報告するという単純なものから、生物学的なリサーチといった複雑なものまで、様々であった。
サリュートには分光計や光電管といった各種の光学観測機器が搭載されていたが、1つ残念だったのは、メインの大型太陽望遠鏡が使用不能の状態だったことだ。これは、サリュートが打ち上げられ周回軌道に達した際、カバーが外れなかったためである。
また、3人はテレビに向かって、実況レポート等も行った。それはほぼ毎日といってもよいほどで、地上からはメディアが彼らに質問を寄せる。3人はカメラの前で、無重力という特殊な状態を生かして、”ウケ”の狙える演出も見せた。ある時は宙返り、ある時は水平泳ぎ…地上ではあり得ない状態を見せつけることで、人々の好奇心をくすぐった。
これらは勿論、ソ連国内だけで報道されたわけではない。プロパガンダの1つとして、世界へ向けても報道された。「サリュートの乗組員は今日、滞在○○日目を迎えた!」等といった、高らかな宣言がこれでもかという程に、続いた。何せ、久しぶりのソ連の“勝利”なのだ。
ちなみに、切手に興味のある人は、ソ連が膨大な量の記念切手を発行していたことを知っている。切手は同国の大事な商売道具の1つであり、オリンピック選手を始めとして、様々な図案が発行された。勿論、宇宙船が打ち上げられるたびに、飛行士や宇宙船がデザインされた切手が発行され、これは80年代のミールの頃まで続いた。当然、記念すべきサリュート1号の3人も切手になっている。
この切手にまつわる話を1つ。旧ソ連時代、西側には宇宙船の正確な形がなかなか伝わって来なかった時、専門家は切手の図柄から、宇宙船の形状を把握していたという。ソ連は、切手の図柄は比較的正確に描いていたようで、そんなところから“機密”が漏れていたとも言えるのが興味深い。(ただ、ボストークやウォスホートなどは、かなりデフォルメされたものもあったが)
いや、ひょっとしたら、むしろ知られるのを意図して、わざと描いていたのかも?ヒミツはさりげなく自慢したくなるのが人間であるが、いかがだろう…?
◇
 話を元に戻そう。実験など、全てのミッションは特に問題なく、順調に進んでいた。1週間が経とうとしていた6月11日、ミーシンやカマーニン、それに政府の上級役員らは宇宙基地からモスクワへ帰った。管制部では、地上で見守る宇宙飛行士達が交代で、3人との交信を担当していた。テレビ中継も順調で、全ては滞りなく進むものと、誰もが思っていた。
話を元に戻そう。実験など、全てのミッションは特に問題なく、順調に進んでいた。1週間が経とうとしていた6月11日、ミーシンやカマーニン、それに政府の上級役員らは宇宙基地からモスクワへ帰った。管制部では、地上で見守る宇宙飛行士達が交代で、3人との交信を担当していた。テレビ中継も順調で、全ては滞りなく進むものと、誰もが思っていた。
飛行開始から11日目の16日昼、モスクワにいた飛行士達の総監督・カマーニンは飛行場へ向かっているところだった。管制部のある、クリミヤ半島へ向かう予定だったが、そこで彼は、サリュートの船内で、焦げ臭い異臭が立ちこめているという報告を受けた。管制部の報告は続き、多分、火災が発生したということ、クルーはソユーズに退避したということも伝えた。サリュートからその第一報を連絡したのは、ボルコフだった。
カマーニンはそのまま飛行場へ向かい、飛行機に乗り込み、出発した。サリュートで何が起こったのか、気が気でなかった。焦っていたに違いない…しかし、離陸から30分後、モスクワ郊外の飛行場へ引き返してしまったのだ。
「この大事な時に、何が起きたのだ?」誰もがそう思ったが、これは、航空管制官の誘導ミスだったことが判明、カマーニンらは結局、2時間ものつまらないロスタイムを消化してしまった!
彼が管制部へ到着したのは深夜で、早速、サリュートと交信を始めた。応答したのは船長・ドブロボルスキー。既に臭いは消え、元の状態に戻っていること、臭いが立ちこめたとき、クルーそして管制部の者達は極度の緊張状態にあったこと等が報告された。ちなみにこの時、ボルコフは就寝についていた。
なお、異臭が充満した直後、パワーケーブルが焼けたのではないかと考え、クルーらは、地上への帰還を打診した。しかし、特にそれ以上の異常がなかったことから、ミッション続行が指示されたという。
だが、ある意味もっと深刻なのは、この事態の最中、ボルコフがドブロボルスキーと激しく衝突したという事だった。彼は、ドブロボルスキーが船長を務めるのが許せず、そのイライラがついに爆発したのだった。火災の際、船長とパチャーエフ、共に新人の2人を無視し、独自に原因を探し当てようとしていたといわれる。
3人、狭い空間に、しかも野郎が長期間閉じこめられたらどうなるか…衝突が起こらないのが不思議だろう。そのような事まで含めて、クルーは常に皆一緒に訓練を受けているのだが、彼らの場合は、度重なる入れ替えで、心理的にチームワークが完成する余裕がなかった。しかも、最大の要因は、ルーキーであるドブロボルスキーが船長に任命されたことである。大抜擢ではあったが、順序で言えば、一度宇宙飛行を経験しているボルコフが勤めるのが筋だった。
◇
宇宙飛行士らは、自分の仕事に格別のプライドを持っている。それは、大海原を命がけで押し渡る船乗りや、ジェット戦闘機で敵と対峙するパイロットのそれに等しい。そして、同じ飛行士同士でも、飛行経験の有無は雲泥の差を生じさせる。誰もが“飛びたい”し、一度飛べば、もう一度行きたくなる。特に、新型の宇宙船に最初に乗れるというのは、輝かしい名誉。しかもその船長となれば、ひとしおである。
因みにこれは、米国の宇宙飛行士とて例外ではなく、アポロのクルーを巡っては、誰もが先を争っている。
我々庶民から見ると、遠い存在のエリートである飛行士達だが、しかし、宇宙開発現場では非常に弱い立場にある。ヘタなことを口にすると、「宇宙を飛べない」という、彼らにとっては死を上回る恐怖が待っている。「飛ばない飛行士はただの人」なのだ。『人類、月に立つ』(アンドルー・チェイキン著 NHK出版)や『ドラゴンフライ』(ブライアン・バロウ著、筑摩書房)には、米国やロシアの飛行士達の、知られざる苦悩が、これでもかと余すところ無く描かれている。涙なしには読めない現実が、そこにある。
ボルコフはついに、自分が船長をやるべきだと言い放った。彼は、新人らの不慣れさに、苛立っていた。「何でコイツの下にいなくちゃならないのだ…」1989年にこの出来事を打ち明けたミーシンは、当時、火災の後、ボルコフとかなり長い、“複雑な話し合い”をしたという…。
◇
6月21日、国家委員会は、クルーらのフライトを27ないし30日まで延長することを決定したが、これに反対したのは、カマーニンだった。彼は、長期に渡る無重力の影響を心配していたのだが、彼の主張はあっさりと却下されてしまった。
カマーニンはこの時、虚無感に襲われたようである。彼は、過去10年間、宇宙飛行士達を仕切る総監督として君臨してきたが、実はこの時、そのポジション自体が脅かされようとしていたのだった。ソユーズ11号の飛行が始まる前の5月22日、彼は宇宙基地からモスクワに移動したのだったが、そこで彼は、自分の地位を揺るがす、不穏な動きがあることを察知している。
その“クーデター計画”の中心は、過去3度の宇宙飛行を経験したシャタロフであった。彼は既に40歳半ばに近い、飛行士の中でも現役を離れることを考える年配であった。
翌22日、カマーニンは決心をした。それは、引退だった。
 彼もまた、時代に翻弄された人生を送った一人だった…第二次大戦ではスターリンに尽くし、長男を戦争で失い、疎開も経験し、宇宙飛行士の監督となってからは、コロリョフやミーシンらと喧嘩の日々。しかも在任中、ソユーズ1号の事故でコマロフを失い、戦闘機の墜落という宇宙とは無縁の事故で英雄・ガガーリンを失っている。
彼もまた、時代に翻弄された人生を送った一人だった…第二次大戦ではスターリンに尽くし、長男を戦争で失い、疎開も経験し、宇宙飛行士の監督となってからは、コロリョフやミーシンらと喧嘩の日々。しかも在任中、ソユーズ1号の事故でコマロフを失い、戦闘機の墜落という宇宙とは無縁の事故で英雄・ガガーリンを失っている。
彼は10月に、63歳を迎えようとしていた。還暦はとっくに過ぎたものの、戦争の記憶がやはり一番、後遺症として残っていた。
もう、彼には戦う気力がなかった。
「若い者に、譲ろう…」
史上初・宇宙ステーションの大成功を、帰還したソユーズ11号のクルーらと祝い、静かに去ることを思い描いたに違いない。
6月26日、3人は全ての予定を終了した。当初4週間の予定だったミッションが、3週間で終わったのだ。彼らは数日かけて、次にやってくる者達のために後かたづけを行った…大掃除である。帰還は29日に設定された。
◇
6月29日、3人はソユーズ宇宙船に乗り込んだ。ソユーズの帰還カプセルを閉じたのは、ボルコフだった。飛行中はいろいろあったが、この時は複雑な心境だった、かも知れない。次はいつ任命されるか、わからない。いや、もう飛ぶことはないかもしれない…何せ、チームワークを乱し、管制部をさんざん振り回したのだから。
ハッチをしっかり閉じたボルコフだったが、目の前にある「ハッチ・オープン」のランプが消えなかった。「はぁ、なんということだ…」ボルコフは管制部に怒鳴った。
「ランプが消えない、どうすればいいんだよ!」
ハッチが閉じないと、カプセルを切り離した際、空気が抜けてしまう。しかも彼らは、宇宙服を着ていない。地上管制部で原因を調べたが、ハッチは確実に閉じている信号が送られてきていた。やや検討された後、「センサーの不具合ではないか」ということになり、ボルコフらが指示通りに調べた結果、確かにそうだった。
3人を乗せたソユーズ11号はサリュートから離れ始めた…歴史的ミッションの最終章が、始まろうとしていた。彼らは、サリュートの周囲を暫く飛行し、写真などを撮った。それは、想い出として残るものだったに違いない。やがて、宇宙船は大気圏突入に備えた体勢に入り、地上管制部から、連絡が入った。
管制部 「グッバイ、母なる大地で再会しよう!」
ソユーズ「ありがとう、また会おう。船は旋回を始めているよ」
大気圏突入の際は、交信が一時的に途切れる。
◇
ソユーズ11号は軌道モジュールと推進モジュールを切り離し、3人の乗った帰還カプセルが予定通り、大気圏に突入した。全ては全自動で行われるので、クルーらは座っていればよかった。予定の高度まで降下すると、カプセル内の空気圧と、大気圧を等しくするためのバルブが開き、パラシュートが展開、祖国の大地に着地することになっていた。
通信不能時間はそう長時間ではなかった。パラシュートが開く際、交信アンテナも引き出されて、管制部との通信が再開される事になっていた。だが、帰還カプセルからの応答は無かった…「アンテナの引き出しがうまくいかなかったのだろう」管制部は楽観視した。実際、パラシュートを一杯に広げ、何事もなく、なめらかに降下する姿が確認され、救助ヘリも追跡を開始していたからだ。救助ヘリは、カプセルが着地する瞬間、逆噴射ロケットが勢いよく点火するのを見た…これも全て、予定通りのものだった。
3人は長期宇宙飛行記録を塗り替え、帰還した。以前ソユーズ9号で飛行したニコライエフらがそうであったように、自力では動けないだろうと皆思い、救助チームがタンカを抱えて周囲を取り囲んだ。カプセルは静かに横たわっていた。
 作業員が横倒しのカプセルのハッチを開き、中をのぞき込んだ…シーンとしている…誰かが物音を発してもよいはずなのだが…次の瞬間、彼らは、3人の息が止まっていることを本能で察知した!(写真・上)
作業員が横倒しのカプセルのハッチを開き、中をのぞき込んだ…シーンとしている…誰かが物音を発してもよいはずなのだが…次の瞬間、彼らは、3人の息が止まっていることを本能で察知した!(写真・上)
事態は最悪を迎えた…3人は、死んでいたのだ。
彼らのシートベルトは外れた状態で、ドブロボルスキーはそれに体がもつれた状態だった。地上と交信するための通信機は全てオフの状態だった。
連絡は直ぐに宇宙基地やモスクワに伝えられた。現場では救助隊が3人を引き出し、心臓マッサージ等を行ったが、彼らが息を吹き返すことはなかった。(写真・下)
直後、「長期の無重力が原因だろう」と推測されたが、検死の結果、急激な減圧、つまり、空気が抜けてしまったことが死因と断定された。ニュースは全世界に伝えられ、日本でも新聞一面で大きく扱われた。栄光で終わる筈のミッションが、悲劇で幕を閉じた。
ソ連国民には、3人は英雄だった。毎日伝えられる彼らの活躍は、アポロに打ちひしがれた心には、“ニューヒーロー”の誕生でもあったのだ。彼らの死は、ケネディが暗殺された時に受けた米国民のショックと同じほどの衝撃を、ロシア人に与えたと言われている。
また、この事故は米国の宇宙ミッションにも重大な影響を与えた。当時、まだアポロ計画は継続中で、アポロ15号が飛び立とうとしていたのだ。アポロに共通する懸念は、無いのか…NASAは事故原因を、ソ連当局に問い合わせた。それに対するソ連政府の返答は、素早かった。
「ソユーズの事故は、気密漏れによるものである。アポロとは構造が異なるので、そちらに何ら問題はない」
…“恐怖と閉鎖の支配”を漂わせる共産主義ソビエトが、宿敵であるはずの米国の完全勝利を後押しした瞬間だった。宇宙開発に関してはこの時、冷戦は終わった、のかもしれない。
 3人は国葬で葬られ、コマロフやガガーリン、コロリョフらが眠るクレムリン壁に埋葬された。米国からは、トム・スタフォード飛行士が代表として参列したが、これは初めてのことだった(コマロフやガガーリンの葬儀には、米からは誰も出席しなかった)。
3人は国葬で葬られ、コマロフやガガーリン、コロリョフらが眠るクレムリン壁に埋葬された。米国からは、トム・スタフォード飛行士が代表として参列したが、これは初めてのことだった(コマロフやガガーリンの葬儀には、米からは誰も出席しなかった)。
(写真:赤の広場での葬儀。レーニン廟の正面に3人の遺影が並べられているのがわかる。画像が小さいのでわかりにくいが、TVカメラなどが並ぶ報道席が左側に設けられている。レーニン廟の上段には政治局員ら、党幹部が参列している。手前にはモスクワ市民が詰め寄せている)
◇
事故の調査が始まり、空気が抜けた原因は、カプセルの内外の圧力を平衡に保つために開くバルブが、予定よりも早く開いてしまった結果、船内の空気が宇宙空間に逃げてしまったことと断定された。カプセルのレコーダーには、約112秒で船内気圧がゼロになったことが記録されていた。空気が抜け始めて10秒かそこらの内に彼らの意識はもうろうとなり、30秒で動けなくなり、50秒後には死に至ったとみられている。
ただ、最大の謎は、なぜバルブが開いてしまったのか、ということだった。同型のカプセルで幾度も再現実験が行われたが、結局、同じ状況を再現することはできなかったという。この、一連の事態を、カマーニンは独自に考察し、「日記」にこう残している。
「宇宙船が3つに分離する際の結合ボルトの爆破において、爆破の勢いが強すぎ、バルブが開いてしまった。彼らはとっさに状況を理解した。ドブロボルスキーはまず、ハッチから空気が漏れていると察知し、それを確かめようとシートベルトを外し、ハッチを確認したが、異常は無いと知った。彼らは多分に、エアの抜ける音を聞いていたはずで、それがどこから来るのか知るため、雑音をうならせていた通信機の電源を全てオフにした。すると、音は船長座席の下にある問題のバルブから出ていることを知り、とっさにそれを閉めたが、タイムアウトになってしまった…」
事故調査委員会は、カマーニンの考察と同様の結論を出し、それが公式の事故原因となった。1990年、ミーシンはこの事故について、「単に、バルブの口に指をあててふさげばよかったが、時間は無かった」と語っている。だがそもそも、バルブが開くという設定は、あり得ない話だった。バルブも2、3回まわせば閉まるようになっていればよかったが、そうはなっていなかった。完全に閉じるには、まだあと半分も回さなければならなかったのだ。
「カマーニンの訓練と指導に落ち度があった」と責める者もいた。だがそれを言うなら、バルブが直ぐ閉まるような設計になっていなかった事こそ、問題なのだが。設計の際、大気圏外で開いてしまった場合の事まで考察に入っていなかったのである。
7月8日、失意の内に、彼はその職を辞任した。後任は、シャタロフだった。
※追記
“Disasters and Accident in Manned Spaceflight”には、帰還直後の様子として、横倒しの状態のカプセルの写真(上参照)が記載されているが、「事故はこうして始まった!
ヒューマン・エラーの恐怖」第2話には、起立した状態にあり、真上に登った作業員がハッチを踏ん張って開けようとしている写真が記載されている。ソユーズの外壁の様子も多少異なるような気がするが…どちらがホンモノなのだろう?それとも、倒したのだろうか…?
【Reference】どの資料も詳しくわかりやすく、推薦です!
Encyclopedia Astronautica (c)Mark Wade http://www.astronautix.com/
“Soyuz” by Rex D. Hall & David J. Shayler, Springer Praxis, 2003
“The Soviet Space Race with Apollo” by Asif
A. Siddiqi, University Press of Florida, 2003
“Disasters and Accident in Manned Spaceflight” by David J. Shayler, Springer
Praxis, 2000
「事故はこうして始まった! ヒューマン・エラーの恐怖」第2話
S.ケイシー著 赤松幹之・訳, 化学同人, 1995
(最後の「事故はこうして始まった!」に記載されているのは、事故を読み切り小説風にしたもの)