プログラムはまだアクティブだ! 〜 あるアフガン戦士の判断 〜
かつて、船長の命令には絶対服従のソユーズで、その操船に口を挟んだ若者がいた。
彼の名は、アブドゥル・アフド・ムハンマド(Abdul Ahad Mohmand)。元アフガニスタン空軍のパイロットである。
ロシアはソ連時代、その同盟国と友好国の結びつきを象徴する催しに、宇宙分野も大いに利用した。それは「インターコスモス」と呼ばれ、旧東欧諸国やアジアなどに広がる社会主義国に参加を呼びかけ、共同で科学衛星などを打ち上げていた。
インターコスモスミッションで華々しいのは、やはり有人宇宙活動であった。ソ連は自慢の宇宙ステーション「サリュート」を大いに活用し、1978年、チェコ人ウラジミール・レメクがソユーズ28号でサリュート6号に向かったのを皮切りに、十数名を数える外国人がソユーズに乗り込んだ。
ただ、一連の有人ミッションは政治的な意味合いの強いものであり、外国人飛行士らはあくまで“ゲスト”。サリュート滞在中は特別何もすることはなく、勿論あちこち触れることも許されず、限られた実験以外はただのんびり時間を潰しているだけだった。
ちなみにレメクが、米ソ両国人以外で初めて宇宙へ向かった人間である。宇宙開発史という観点からは、ムーン・レースを中心とした米ソの独占状態に風穴を開けた意味は大きい。しかし冷戦構造という世界情勢の中では、彼、そしてその後に続いた外国人飛行士らに対する西側の評価は、プロパガンダの片棒を担いでいるに過ぎないというのが大勢であった。
ムハンマドがソユーズに乗り込んだのは1988年の夏だった。ミハイル・ゴルバチョフ書記長の下、「ペレストロイカ」「グラスノスチ」を合い言葉に改革・開放が進められていたソ連であったが、彼の飛行はそれまで同様、政治と無縁ではなかった。
少しだけ、アフガニスタンの近代史に触れてみたい。
◇
アフガニスタンは中央アジアの内陸国で、数百年も昔から東を中国、南をインド・パキスタン、西をペルシャ(イラン)、そして北をロシアに押さえられた、まさに大国の狭間にある地域である。他民族の文化が乱立する一方、領土をせめぎ合う大国に翻弄され続け、有史以来戦乱の絶えない場所。19世紀は覇権を目指す英国と3度の大戦争を繰り広げ、近代アフガニスタン(以下、アフガン)として独立を果たしたのは1919年のことであった。
第2次大戦後は王政の下で平和を楽しみ、数多く残された文化遺産を目当てに世界中の観光客は“文明の十字路”アフガンを目指し、70年代始めにかけて観光業を中心に空前の潤いをみせた。
しかし、1973年、王位にあったザーヒル・シャーが従兄弟であるムハンマド・ダーウードによる共和制クーデターで追放され、王政も廃止。ダーウードはもともと首相であったのだが、その性急な政策が反発を招き、追放されていたのである。
ダーウードは首相在任時、国軍の近代化を第一急務と考えた。その指導と援助を仰いだ相手がソ連で、アフガンがソ連と深く結びついたのはこの時である。ソ連としても戦略上、この地の支配は極めて重要であったのだ。
だが、その彼の性急かつ強硬なやり方は皮肉にも国軍の反発を招き、1978年4月、軍事クーデターが勃発。大統領にあった彼とその一族は処刑され、同じく親ソ派であったハーフィズッラー・アミーンが大統領に就任。しかし国内は、ムジャヒディン(イスラム教徒戦士)を中心とした反ソ連ゲリラとの内戦に突入、荒廃が始まった。
その上具合の悪いことに、1979年春、イランでルーホッラー・ホメイニによるイスラム革命が成立。ソ連政府はこの動乱が、イスラム民族が多数を占めるソ連南部に飛び火することを大いに恐れたといわれる。事実、ソ連は早くも同9月、国境付近に部隊を集結させ軍事演習を行ったが、米国はこの不穏な動きに警告を発している。
1979年12月。ソ連はついに、国際社会を震撼させる行動に出た。クリスマスイブの12月24日、8万5千人と言われる兵力でアフガンへの侵攻を開始したのである。彼らの目的は指導力の弱いアミーンの排除とより強固な傀儡政権の樹立、イスラム原理主義の封じ込めにあったが、当時「雪解け」「デタント」と言われた米ソ対話は崩壊、東西関係は再び冷え込んだ。
やもすれば庶民には遠い国の出来事のように感じられるこの軍事行動を、大変な事態なのだと感じさせたのは、オリンピックだろう。1980年7月にモスクワ五輪が開かれる予定であったが、アフガン侵攻から1ヶ月も経たない同年1月、米国は同大会への不参加を表明。それに追従するように、日本を含む西側各国が不参加を決定し、多くの選手達が涙を流した。
ボイコットは止まらない。4年後の1984年、この年開催のロサンゼルス五輪に今度はソ連・東欧勢が参加を拒否。政治とは無縁であるはずの選手達が、政治の都合によるボイコット合戦に翻弄され続けたのであった。
◇
 アブドゥルアフド・ムハンマド(右)は1959年1月1日、アフガニスタン・ガズニー州に生まれたパシュトゥーン人である。1976年、カブール工業大学に入学後、78年軍に招集され、教育生としてソ連に派遣。クラスノダールとキエフの航空学校で学び、帰国後アフガン空軍に配属された。87年、同国空軍アカデミーを卒業している。
アブドゥルアフド・ムハンマド(右)は1959年1月1日、アフガニスタン・ガズニー州に生まれたパシュトゥーン人である。1976年、カブール工業大学に入学後、78年軍に招集され、教育生としてソ連に派遣。クラスノダールとキエフの航空学校で学び、帰国後アフガン空軍に配属された。87年、同国空軍アカデミーを卒業している。
1987年7月20日、ソ連とアフガンは共同飛行に関して合意に達し、同9月30日、正式決定された。フライトは当初1989年の前半に行われることになったが、これは通常の飛行士訓練期間が18ヶ月であることを考えると当然の日程であった。
最初の選定作業は1987年11月から12月にかけて行われた。457名が候補として選ばれ、そのうちの52名が次のステップへ、そして最終的に8名が選抜に残ったという。彼らはモスクワへと派遣され、更なる選考を受けることになった。そこで残るのは、2名だった。
彼が飛行士として決定したのは翌1988年2月13日で、もう一人のムハンマド・ドーランと共に訓練を受けることになった。両者とも経験豊富なパイロットで、ロシア語に堪能で、航空力学に明るかったという。宇宙飛行士訓練センターで訓練が始まったのは、同25日だった。
しかし、同年4月、飛行予定が僅か4ヶ月後の8月と大きく繰り上げられることになり、訓練メニューは大きく削られることになった。例えば耐寒サバイバル訓練などは、ミッションが夏ということもあり、不要なものとして削除されただろう。
インターコスモスのゲスト飛行士の場合(注・補足1参照)、訓練期間は4期、すなわち第1期(約6ヶ月)、第2期(2ヶ月)、第3期(4ヶ月)、第4期(約5ヶ月)に分けられていた。第1期、第2期では天文学や航法学、それにロシア語などの詰め込みが行われるが、既に彼らがこれらに習熟していたのであればここは大きく削減することができただろう。また、第3期では搭乗する3名のチーム行動が始まり、家族ぐるみの交流も行われ、より強い連帯感の構築が図られる。これも、大幅に削ろうと思えばできないこともない。
なにせ、間に合わせでも成功すればそれでいいミッションなのだ。事実、クルーの連帯感構築とはいえ、本質は“ゲスト”の扱い。シミュレーター訓練の段階で既に、許可がなければ触れることすら許されなかったのであり、事実、先述のレメクは「ちょっとでも触れようものなら船長から手をひっぱたたかれたものだ」と後に証言している。
このエピソードは、主従関係が絶対であることを象徴している。乗員は船長に絶対服従であり、ましてゲストはロシア人より更に下なのだ。しかしその船長もまた、管制部のコントロール下に置かれていることを忘れてはならない。操船や作業変更など重要な判断は、自分の頭で考える前に管制部の指示を仰ぐよう植え付けられたのである。
船長の命令が絶対であるというのは当然としても、その船長が思考よりも指示待ちを優先するよう強いられるというのは非常に危険である…奇襲してきた敵を目の前に、射撃の許可を上層部に求めるようなものだ。
◇
それにしても彼の選抜から打ち上げまでの流れは、非常にバタバタしている。
アフガンで飛行士候補がかき集められたのは87年の秋で、そのわずか数ヶ月後には正式決定が下り、更にその半年後の8月末にはソユーズに乗り込み、宇宙へと向かったのだ。
このバタバタ飛行の理由をソ連は公式に明らかにはしていない。だがその背景にあったのは、ソ連軍のアフガン撤退だった。ソ連は1988年4月14日、アフガン、パキスタン及び米国と共に、アフガンの事態を収拾させるための4ヶ国和平調停を結んだ。これは1ヶ月後の5月15日に発効し、同日よりソ連軍はアフガンからの撤退を始めたのである。
しかも、その半数が同8月15日までに撤退するという、性急なものだった。
この調停の目的は、混乱にひとまず終止符を打つことであり、国際社会は大歓迎した。勿論、ゴルバチョフによる改革の一端であり、書記長に就任した翌年の86年7月28日、ソ連軍の一部撤退を表明。同10月には約8000人が帰還し、ウソではないことを強くアピールしている。
一方、アフガンではこの2ヶ月前の同5月、最高指導者であるアフガン革命評議会議長に、元アフガン秘密警察長官だったムハンマド・ナジーブッラーが就任。彼は87年1月、停戦を提案、ゲリラ側は信用しなかったものの、一方的停戦に入った。7月にはソ連を訪問し、部隊撤退の確認を行い、11月30日には新憲法を制定、自身は大統領に就いた。
88年に入ると、和平へ向けた動きが更に加速していく…。
かくしてソ連・アフガン友好の象徴飛行は、平和が戻りつつあることのアピールへとすり替えられ、タイムラインが大きく前倒しされたと考えるのが自然と言える。しかも彼の滞在先はかつてのサリュートではなく、新型ステーション「ミール」。ミールとはロシア語で「平和」を意味する…これほど打って付けの場所はない。
余談だが、この年の9月にはソウル五輪も予定されており、12年ぶりに米ソ両陣営がそろって参加することになっていた。五輪が始まる9月17日のほぼ2週間前のソユーズ飛行は、このイベントにも華を添えることになる…。
◇
ムハンマドと共に搭乗する2名のロシア人は、ウラジミール・リャホフとワレリ・ポリャコフ。リャホフはこれが3回目の飛行であり、船長を務める。1941年7月20日生まれの彼は1967年5月に選抜され、初飛行は1979年。2度のサリュート長期滞在を経験し、この時点で宇宙滞在日数は330日に迫ろうとしていた。このミッションでは約1週間のミール滞在の後、ムハンマドを連れて戻る予定だ。
一方、ポリャコフはこれが初飛行。1942年4月27日生まれの医師であり、1972年3月、宇宙飛行医師チームの一員として選抜されていた。彼はそのままミールに残り、長期滞在を目指す。医師として、他のクルーらの体の変化を探るのが主な任務だった。余談だが、翌年4月に帰還した後、1994年1月に再びミールへ向かっている。この時には1年3ヶ月もの滞在を行い、これら2度の長期滞在は通算678日と16時間半。勿論、未だ破られていない記録である。
この時、ムハンマドは29歳であった。18歳も年上のリャホフとポリャコフとは、ややもすれば親父と息子の間柄といってもあり得なくはない。
(左からムハンマド、リャホフ、ポリャコフの3名。右はミッションパッチであり、彼らが着用している宇宙服の右胸に貼り付けられているのがわかる。ポリャコフはそのままミールに留まり長期滞在ミッションへと入るため、“ソ連・アフガン共同飛行ミッション”のパッチは付けられていない。)


乗り込む宇宙船は「ソユーズTM」宇宙船。これはソユーズ宇宙船ファミリーでは「ソユーズ」「ソユーズT」に続く、いうなら第3世代に当たるもので、彼らが乗るのはその6号機であるソユーズTM6であった。
ソユーズTMは、ソユーズTを改良したものである。そもそもソユーズTはサリュートへの物資輸送能力を高めたもので、“T”は“Transport”(輸送)の頭文字。その修正版であるTMの“M”は“Modificasion”(修正)を意味している。
サリュートを発展させた宇宙ステーション「ミール」の運用にあたり、人員輸送手段であるソユーズTの性能アップが図られたのである。接舷ポートの変更なども余裕を持って行えるよう搭載燃料の増加や、ソロでの長期飛行も可能であるよう食料などの生活物資の積載増加などが行われている。
下はソユーズTM宇宙船のカットアウェイ。全体は3パートから成り、それぞれ「軌道モジュール」(Orbital
Module)、「帰還モジュール」(Decent Module)、「機関モジュール」(Service
Module)と呼ばれている。卵形の軌道モジュールには食料や衛生用品、各種科学機器などが搭載され、先端はステーションとのドッキングポートになっている。飛行士らが乗り込むのは帰還モジュールだが、乗り込む際は軌道モジュールの側面ハッチから入る。座席は扇状に配置されるが、その配置は上の集合写真の通りである。
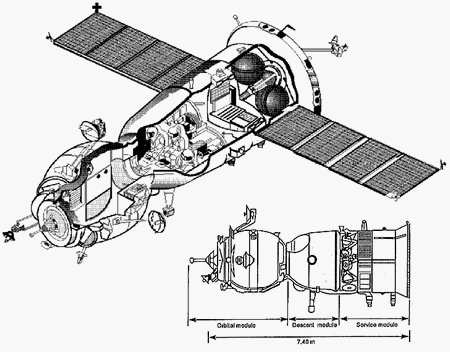
機関モジュールには燃料やエンジンなどが備えられ、外には2枚の太陽電池パネルが装着されている。このモジュールは推進の要である。
ちなみにリャホフ船長は過去ソユーズ32号、ソユーズT−9に搭乗し、サリュート6号、サリュート7号に滞在している。彼はこれで、各々3種類の宇宙船とステーションを経験することになる大ベテランだった。
また、今回のソユーズTM6での飛行には、通常乗るはずのフライトエンジニアが乗っていない。これは、リャホフには元々ソロ飛行のミッションが予定されていたからだ。当時彼はミールに対する「救命ミッション」を想定した単独飛行訓練を受けていたところであり、補佐をするフライトエンジニアは必要としなかったためである。
◇
1988年8月29日早朝、バイコヌール宇宙基地は打ち上げに向けて最後の仕上げに入っていた。ロケットは第1番発射台、通称「ガガーリン発射台」と呼ばれる射点に据えられている。液体酸素、ケロシンの充填はほぼ完了し、脇からは気化した液酸で生じた水蒸気の白煙をシューシューと吹き出し、打ち上げを今か今かと待っている。
作業員が忙しく、しかし手際よくプロセスを進めていく。彼らは数多くのロケット打ち上げに関わってきた熟達した部隊なのだ。時々大きな問題も発生はするが、もはや生命が奪われるような事故は全くなく、作業はルーチン化した、単調なものとなっていた。
一方、政府高官などの見学者達が、見学ポストに集まり始めた。ここは射点から何キロも離れた安全区域。簡単な小屋であるが、傍には赤地に白抜きのロシア文字が並んだ横断幕も揺らめいている。「ソ連・アフガン友好の証!」だろうか、それとも「共産主義の輝かしい勝利!」だろうか、それは知らない。だが、ソ連の街並みのあちこちで見られたような普通の、皆を鼓舞するスローガンであったことは間違いなかろう。
現地時間・午前7時23分(世界時・午前4時23分)、ソユーズは真夏の大空へ轟音と共に飛び上がった!早朝のそれは、ステップに住む生き物たちの眠りを覚ます!バリバリバリと空気を引き裂く音を彼方まで轟かせながら、一気に天空を目指すソユーズ。
見学ポストでは多くの人々が首を上げていく。黙って見つめるものもいれば、歓声をあげるものもいる。
全ては順調で、お決まりの手順で地球周回軌道へと昇っていく…10分後には周回軌道投入だ。
これまたお決まりの事だが、打ち上げ成功が国営タス通信、それにモスクワ放送を通じて全世界に伝えられた。ペレストロイカはどこ吹く風とばかり、高らかに伝えられるその第一報は、旧時代の雰囲気をタップリと湛えている。
一方、アフガンのナジーブッラー大統領は同日、ソユーズ飛行期間中の停戦を発表した。
実のところ、ソ連軍の撤退が和平をもたらす気配は全くなかった…ナジーブッラーとその政権は、ソ連軍の後ろ盾の上に成立していたものであり、皮肉な話だが、ソ連軍の存在が地域の軍事バランスをかろうじて維持していたのである。そこにソ連軍の撤退が本格的になってくると、ゲリラも各地で大規模な攻勢を仕掛けてくるようになったのだ。連日伝えられる激しい戦闘、ゲリラの攻勢が大規模であることを認めるソ連軍。
ゲリラを支援していたのはパキスタン。パキスタンを支援するのは米国。やむにやまれず応戦するソ連軍。「協定違反!」の非難合戦…。
◇
3人を乗せたソユーズは31日、無事、ミールとドッキングした。この時、ステーションに滞在していたのはウラジミール・チトフおよびムーサ・マラノフの両飛行士。彼らは前年12月21日、ソユーズTM4でミールに到着、第3次長期滞在クルーとして活動を行っていた。
ちなみに6月、インターコスモスミッションの一環でブルガリア人アレキサンドロフ・パナヤトフがソユーズTM5でミールを訪問している。この時には船長及びフライトエンジニアのロシア人を含む計3名でのフライトであったが、約1週間の滞在の後、3名とも地球に帰還している。注意したいのは、この時彼らが帰還に用いた宇宙船は「TM4」であったことだ。
少々ややこしいので、簡単な表としておこう。行きと帰りで乗る宇宙船が異なる点に注意しておきたい。
| 宇宙船 | 期間 | クルー | 備考 | ||
| TM4 | 87.12.21-88.12.21 | チトフ | マラノフ | レフチェンコ | 3名ともロシア人。レフチェンコは接舷していたTM3で一週間後に帰還。チトフとマラノフが第3次長期滞在クルー。 |
| TM5 | 88.06.07-88.06.17 | ソロビヨフ | サビニク | アレキサンドロフ | ブルガリア人アレキサンドロフのインターコスモスミッション。3名ともTM4で10日後に帰還。 |
| TM6 | 88.08.29-88.09.07 | リャホフ | ポリャコフ | ムハンマド | リャホフとムハンマドがアフガン共同ミッションクルー。両名はTM5で10日後に帰還。 |
宇宙の長期滞在というと我々から見ると羨ましい話に聞こえるが、当の飛行士らにしてみると、10日も経つと飽きてくるという。彼らにとっての楽しみは、プログレス宇宙貨物船で定期的に送られる様々な娯楽用品や家族の手紙であったが、最たるものは、インターコスモスなどの“訪問客”であった。
ムハンマドやリャホフらは、第3次クルーにとっては6月のインターコスモス以来、2ヶ月ぶりの客人であった。TM6が到着すると彼らは抱き合って喜んだ。
ムハンマドはミール滞在中、ロシア人飛行士らにアフガンティーを振る舞ったり、祖国の地を撮影するなどして過ごした。その中では、ナジーブッラー大統領との交信も行われたが、これもまた、政治的アピールとして利用された。
しかし。ムハンマドが想いを馳せるアフガンの大地では、混乱が増しつつあった。ゲリラによるロケット弾攻撃、爆弾テロが続く…危険な状態に陥ったソ連軍部隊は反撃に出たが、それを米国は協定違反と批難する。ゲリラは首都カブールのソ連軍武器庫への大規模な攻撃を行ったが、これは撤退開始以降、最大級の攻撃だった。
ソユーズ打ち上げ直前の28日、ナジーブッラー大統領は国民議会で、「我々は史上、最も堅実で強力な政府になっている」と演説している。だが、共同飛行の間も鳴りやまぬ、いやむしろ激化する砲撃。もはや、アフガンに和平が訪れるとは誰も思っていなかった…。
9月5日の間もなく日付が替わろうとしていた頃、ムハンマドらの帰還の時がきた。ミールに残る3人はムハンマド、それにリャホフと固い抱擁を、別れの挨拶を交わした。
両名は、ソユーズTM5に乗り込んだ。船長はリャホフ。全ては滞りなく進み、予定時刻にドッキングポートから離脱、ミールに別れを告げた。順調に進めば、この後まず軌道モジュールが切り離され、続いて逆噴射を行い高度を落とし、最後は機関モジュールを切り離して、2人が乗った帰還モジュールが大気圏に突入する。
しかしこの後、危機一髪のトラブルに見舞われることになろうとは、現時点で2人は知らない…。
◇
リャホフ船長は、帰還シーケンスの開始を確認した。やがて、軽いショックが宇宙船を揺らす…軌道モジュールが切り離された衝撃だった。各モジュールはボルトでつながれており、離脱は仕込み火薬の爆破で行われる。火薬は確実に爆裂したのだ。それはリャホフにとっては3度目の経験であったが、ムハンマドにとっては初めての経験であり、訓練で教えられていたこととはいえ、軽くテンションがあがったことだったろう。
2人の目の前にはハッチがある。その先にもはや部屋はなく、真空の宇宙が広がっているのだ。
続いて迎えるのは逆噴射だったが、しかしこの直前、トラブルが発生した。ちょうど宇宙船は夜の部分を飛行していたのだが、逆噴射の直前、昼の側に抜け、センサーに入った太陽光がコンピュータを混乱させてしまったのだ。
ナビゲーションコンピュータは、そのバックアップも含めて、宇宙船の姿勢を見失ってしまった。ソユーズTMは改良された最新バージョンだったとはいえ、自身の姿勢を検出する仕組みは旧式のままだったのである。注意事項として、逆噴射開始までの10分以内に、昼夜の境を通過してはならないことになっていた。これは、コンピュータに混乱を与えないためであった。
コンピュータはエンジン停止のシグナルを発した。しかしシーケンスは継続されており、7分ほど経過したところでコンピュータは落ち着きを取り戻し、再び逆噴射を開始した。
「ここで逆噴射は困る」
リャホフはそう判断した。というのも既に予定から7分も過ぎており、ここで大気圏に突入したら、着地点は3500kmも離れたところになってしまうからだ。当然だが地上回収部隊が大変な目に遭ってしまうし、自分たちの安全性も問題になる。脳裏には、ウォスホート2号の例が過ぎったはずだ(開発史2参照)。
彼は噴射開始6秒後に、エンジン停止キーを押した。地上ではモスクワ放送が、ソユーズの帰還延期を報じ、世界がどよめきだった。しかし彼ら、そして地上管制部は、宇宙船は正しい姿勢を維持しており、他には何の問題もなく作動していると確信していたため、全く落ち着いていた。
管制部は、地球を2周したところで逆噴射を再開する決定を下した。
◇
今度は、問題のセンサーを使わず、別の制御装置を使用して機体のコントロールを行うことになった。だが、逆噴射を開始したものの、予定では230秒の噴射が、僅か6秒で停止してしまったのである。
これは、バックアップコンピュータに、前回の飛行データがそのまま残っていたのが原因だった。上述したが、彼らの乗っている宇宙船は、インターコスモスで使用されたTM4である。その6月の飛行プログラムをクリアするのを忘れていたため、バックアップコンピュータが“勘違い”を起こし、メインコンピュータが混乱、エンジンを停止してしまったのだ。
「!?!?」
とっさに目の前のエンジン噴射キーを押し込んだリャホフ。船の姿勢は正しく、このまま噴射を続ければ間違いなく帰還できると判断したからだった。
しかし、僅か7秒後、エンジン再停止。リャホフがキーを押し込み、再噴射を始めたのもつかの間、14秒後に再々停止…。
リャホフは再度、キーを押し込んだ。「何をやってるんだ…!」恐らくイライラと緊張はピークだったに違いない。だがそんな船長の命令を無視するかのように、33秒後、エンジンは虚しく停止してしまったのである。
「ふぅ…」
噴射時間は合計54秒…これではどうすることもできない。
原因は、この第2回目の帰還試みに先立ち、地上管制部がソユーズのメモリーにアップロードしたソフトにあった。最初の試みで6秒間の噴射が行われたことが考慮に入っていなかったことが影響したと言われている。
「やれやれ…ダメみたいだな。管制部の指示を仰ぐしかないな…」
リャホフはそう思っただろうか。万策尽きた彼は一息入れるように、深いため息をついた…かもしれない。
やや疲れ気味のリャホフと、船長の言うことを聞かない船とを、ただ見ているほかなかったムハンマド。勿論、操船に口を挟むことはできなかったが、この時独自に、目の前の計器のチェックを始めた。
彼は、戦闘機パイロットとして、緊急事態には自機の全容把握を直ちに行うよう訓練を受けていた。それが染みついていたため、半ば本能的に、計器を目で追い始めたのだ。
一方、リャホフは、自分の任務を終えたかのようにシートに座って動かない。そんな彼をさほど気に留めず計器を見つめていたムハンマドは、間もなく、大変な事が進行していることに気づいた。
プログラムがまだアクティブだったのだ。エンジン停止で一端終了したシーケンスだったが、10秒後に再開していたのだ。しかも次に予定されていたのは、20分58秒後、機関モジュール爆離だったのだ!
これが何を意味するか。宇宙船の姿勢制御も、逆噴射も全てはこの機関モジュールが担っている…この離脱はいわば、手足を奪われてしまうことになるのだ。2人を乗せた帰還モジュールは、地上へ帰れなくなってしまう!
ムハンマドはとっさに声を発した。「プログラムがアクティブだ!機関モジュールが離れてしまう!」
「?」
リャホフは一瞬、このアフガンの若造は何を言っているのだと眉をひそめただろう。だが彼は大ベテランだ。とっさにその意味を察知した!
ボルトの爆破まで、残り20分。
この時、宇宙船は管制部と交信できない領域を飛行していた。リャホフは独断でこの“時限爆弾”のタイマーを止めようと試みたが、うまくいかなかった。
焦るリャホフ。何度も何度も繰り返したがカウントダウンは止まらない。
「くそっ!なんてことだ!!」
交信不能は僅か20分かそこらであったが、これほど長い20分は、なかっただろう。もはや、全ての進行を停止する緊急コマンドを起動する他なかった。
やがてソユーズが交信可能領域に入った。リャホフは即座に無線で管制部に状況を伝えようとした。この時、機関モジュール分離まであと2分14秒。
緊急コマンド起動許可を管制部に求める彼。しかしどうしたことだ、管制部は応答しない!
まだ無線が通じる範囲ではなかったのか、それとも管制部も動転したのか、それはわからない。ただ、ピンチの2人にとって、そんなことはどうでもよかった。リャホフは返答を待たずに、キーを押し込んだ!
◇
…タイマーは、止まった。モジュール爆離まで、1分を切っていた。
「ムハンマドが独断で状況把握をしなかったら?」「リャホフがムハンマドの声を無視したら?」「リャホフが管制部の返答を待ち続けていたら…?」
せめて船長が、現状把握を行っていたら、そして、管制部の判断を仰がずとも緊急コマンドを押せるような柔軟性があれば…あれほど緊迫した20分を過ごす必要はなかったはずである。
船長が悪いわけではない。指揮系統がギツギツで、船長から判断力を奪っていたのが問題だったのである。
やがて管制部が応答し、状況の確認が行われた。フライトデータとソフトの確認が徹底して行われることになり、24時間の帰還延期が下された。
しかし。この24時間は2人にとって第2のサバイバルになろうとしていた。
既に、軌道モジュールを切り離してしまったことを思い出して欲しい。余裕のある食料や水、酸素や衛生品は全て軌道モジュールに備えられていたのだ。
それなら一旦、ミールに戻るという選択肢もある。搭載燃料も充分で、それは可能であった。だが、ミールとのドッキングポートは軌道モジュールなのだ。
では…ランデブー飛行を行い、宇宙遊泳でミール(もしくはミール接舷のTM6宇宙船)に乗り移る手はどうか?だが、これも駄目だ。彼らが着用している宇宙服は船内用なのだ。
帰還モジュールに残されていた食料や水、それに酸素はもって2日分だった。飛行士が同モジュールに閉じこめられた例として、1976年10月のソユーズ23号がある。クルーは凍てつくテンギツ湖で半日近く閉じこめられたのだが、この時は空調、それに船内温度が問題だった(開発史16参照)。それが、再び繰り返されようとしていたのである。
船内の温度は10℃まで下がっていた。空調システムは軌道モジュールと一体で機能するようになっていたため、そのモジュールを持たない今、空調は効かなかったのだ。
管制部は、船内宇宙服を脱ぐように指示した…船内用は真空には強いが、温度変化には弱い。ソユーズ23号の時、クルーは宇宙服を脱いで暖かい防寒着を着込んだ。今回の場合、ミッションの時期からして防寒着は積んでいなかったと思われるが、ちょっとした布製の衣類は載せられていたのだろう。
しかし2人は、宇宙服を脱がなかった。極めて狭い船内でそれを脱ぐのは大変な作業であり、貴重な酸素を余計に使ってしまうと考えたという。事実、ソユーズ23号クルーらは脱ぐのにカッターも用い、時間も1時間半かかってしまったのである。
加えて彼らが難儀したのは、トイレだった。簡易トイレは軌道モジュールにあったのだ。どうしようもない彼らは、ムハンマドがミールから持ち帰ったバッグに用を足してしのいだ。
「ガバリッ モスクバ。…」 (こちらはモスクワ放送局…)
クレムリン宮殿の鐘の音に続いて、モスクワ放送がニュースを開始、ソユーズ帰還を1日遅らせる発表を行った。グラスノスチのおかげか、状況は正確に伝えられたが、世界のメディアはこれをセンセーショナルに扱った。
これには、ソ連当局の発表に原因があった。当時の新聞報道の一例を見てみよう。
| ソユーズ 帰還を1日延期 「深刻な技術的問題」発生 初のソ連人とアフガニスタン宇宙飛行士による共同飛行を終え、宇宙軌道ステーション・ミールから切り離され、六日早朝地球に戻る予定だったソユーズTM5宇宙船が、「深刻な技術的問題」から帰還を一日延期した。ソ連国営タス通信が同日伝えたもので、アフガニスタン人飛行士ら二人の地球帰還に不安を投げかけている。 タス発表によると、ソユーズTM5はモスクワ時間六日午前二時五十五分(日本時間同七時五十五分)ミールとのドッキング状態を解き、地球帰還の準備に入った。ソユーズTM5はおよそ三時間後の午後六時(同十一時)に着陸する予定だったが、「着陸プログラムの作動が自動的に停止した」ため、帰還の一日延期が決定された。 またソ連宇宙総局の当局者は同日「深刻な技術的問題が生じた。地上の指令で原因の除去に努めている。明日の午前五時(同七日午前十時)に地球帰還をセットしたが、着陸プログラムの変更または手動による着陸の選択を迫られている」と語った。 (中略) 六日未明当初の予定に従ってポリャコフ医師がミールの飛行士の健康管理のため残留、リャホフ船長とモマンド飛行士の二人がミールとドッキング状態のソユーズTM5に乗り換え六日未明地球への帰還についたが、最後のドタン場でトラブルが生じてしまった。 六日夕のタス通信によると、ソユーズTM5の船内の生命維持装置は二日間しかもたないという。 【毎日新聞 1988年(昭和63年)9月7日(水曜日)朝刊 国際面】 |
ソ連当局が、「深刻な技術的問題」、「選択を“迫られている”」という表現を用いていること、その上タス通信が「生命維持装置は2日分」と報じたことが、世界の関心を煽ったのだ。
また、モスクワ放送の解説者が「無事帰還を祈るが、事態は深刻でもある」などと語ったことも影響が大きい。このようなハラハラさせる表現は異例のものだったのだ。
世界のメディアは飛行士らの安否を案じる一方、時間が経つにつれ「物資が底をつくまであと〜時間」というカウントダウンまで流すものも出てきた…。
クルーが元気であることを繰り返し報じるモスクワ放送。生きていることをアピールするため、録音しておいた音声を流すこともした。2日分の非常食が備えられていること、事態の把握は確実に行われていること、そして、翌日早朝に帰還を試みることと、どのような場合でも救助活動の準備ができていることなども報じた。
筆者の想像だが、リャホフの報告を受け取った管制部は、実際、混乱に陥っていたと思われる。帰還失敗がプログラムの不具合なのか、それともエンジンに問題があるのか全く判断がつかない状態だったようで、まずエンジンのチェックから行い、それが正常であることを確認すると大きな安堵に包まれたようなのだ…原因がプログラム側にあるのであれば、最悪、手動でエンジンを吹かせば何とかなる。
◇
6日遅く、管制部はリャホフに対し、コンピュータプログラムを読み上げた。彼はそれをマニュアルで入力するように命じられており、手作業で打ち込んでいく。
全てが完了すると宇宙船は軌道離脱を開始した。逆噴射は予定通りの時刻に、予定通りの時間行われた。間もなく機関モジュールが爆離し、2人を乗せた帰還モジュールが大気圏へ突入。パラシュートを広げて滑らかに降りてくるそれは、予定通りの地点に着地した。
タス発至急電が、世界を駆け巡る!二人の無事帰還が配信され、モスクワ放送も音楽番組を中断、速報として伝えた。
第一報は我が国でも報じられ、夕刊の一面に載せた新聞社もあった。
| ソユーズ 無事帰還 故障克服、一日遅れ ソ連とアフガニスタンの飛行士を乗せ、一旦は地球帰還に失敗したソユーズTM5宇宙船はモスクワ時間七日午前四時五十分(日本時間同九時五十分)、ソ連中央部カザフ共和国内のジェズカズガン市の南東百六十キロの地点に無事着陸した。モスクワ放送が同日午前五時半すぎ、音楽番組を中断してニュース速報として伝えたもので、同速報は、ソユーズTM5の帰還で「ソ連、アフガン共同飛行は成功裏に終了した」と述べた。 また国営タス通信も、無事帰還を速報し「ウラジミル・リャホフ船長(47)、アブドル・アハド・モマンド飛行士(29)の着陸後の気分は良好である」と伝えた。 (中略) 六日夕のタス通信は、ソユーズTM5の船内の生命維持装置は二日分だけで、八日未明には備蓄酸素などが切れると報道し、二人の安否に世界中の関心が集まっていた。 【毎日新聞 1988年(昭和63年)9月7日(水曜日)夕刊 一面】 |
帰還会見でリャホフは、二度目のエンジンシャットダウンの直後、マニュアルでの降下を試みようとしたという。それ故エンジンキーを押し込んだのだが、その後どうなるのかわからず不安であったともいい、「再度発生したシャットダウンは半強制的に行ったためのリスポンスで、自分の判断がエラーだと思った」と語った。「この時の自分は地上に帰りたい一心だった」と認めている。
西側メディアはこれまたセンセーショナルに扱おうとしたものの、ソ連当局は「リャホフの判断は極めて適切なもので、その後見舞われたであろう深刻な危機を回避できたのである」と、極めて冷静だった。
彼はまた、軌道モジュールは大気圏突入開始の直前まで切り離すべきではないと進言している。
一方、ムハンマドは後年、「この間、恐怖よりも緊張で張り詰めていた」と証言している。
◇
ムハンマドは翌8日、「ソ連邦英雄」の称号と「レーニン勲章」を授かり、程なく帰国、アフガン宇宙研究所に勤務した。
だが、ソ連軍撤退後のアフガンは、共通の敵を失ったゲリラの派閥間抗争が勃発。和平は夢と化し、荒廃していく国土。そんな中、厳格なイスラム法に基づく統治を目指した神学徒、いわゆる「タリバン」、の勢力が急速に拡大していく。
1996年9月、タリバンはカブールを制圧、当時幽閉下にあったナジーブッラー元大統領を公開処刑した。この混乱下、たまたま海外出張で国外滞在中だったムハンマドは帰国できなくなり、そのまま難民となった。
現在、ドイツのシュツットガルトで印刷会社に勤務している。
※補足1
ムハンマドはインターコスモス飛行士ではないが(インターコスモス飛行士は各国から一斉選抜、グルーピングされていた)、課された訓練メニューはほぼ同じであった。外国人飛行士の場合、前半の訓練ではロシア語レッスンに特に力が入れられている。
ちなみに彼は、元々バックアップであった。もう一人のメンバーであるドーランが宇宙へ出る予定であったが、疾病が見つかったため入れ替えられたのである(疾病とは表向きの理由で、実は彼がタジク人であったことが入れ替えの理由という説もある)。彼は現在、生死不明である。
※補足2
後日判明したことであるが、第2回目の噴射(合計54秒)があと少し続いていたら、そのまま大気との摩擦で高度を落としていき、弾道突入に入っていたと考えられている。この場合、温度が設計上限を超え、シールドは持ち堪えなかった可能性が高かったという。
※補足3
ソユーズTM5の帰還延期は日本時間で9月6日の早朝に決定したことであり、その後情報がある程度まとまるまで時間がかかったのか、当日の夕刊には記載しなかった新聞社も多い(関心を示さなかった可能性も?)。
6日夕刊のみならず、7日朝刊に記載しなかった社も多かったが、さすがに帰還成功は殆どの社が報じている。ただし、事の一部始終を7日夕刊に記載したところも多いようで、その場合、8日朝刊では扱われていない。
興味深いのは、共同飛行中の停戦発表を報じなかった新聞社が多いことだ。停戦発表は、それだけでも報道優先度は高いと思われるのだが…テレビ報道での扱いはわからないが、日本の新聞メディアは和平を絡めた共同飛行に無関心だったようである。それとも、プロパガンダ見え見えの停戦発表を敢えて無視したか…?
【Reference】
Afghanland.com http://www.afghanland.com/history/spaceafghan.html
アフガン情報 http://homepage3.nifty.com/afghan/
Spacefacts http://www.spacefacts.de/
“SECRETS OF SOYUZ” by James Oberg, Launchspace Magazine March/April 1999,
online http://www.jamesoberg.com/soyuzsecret.html
“Soyuz” by Rex D. Hall & David J. Shayler, Springer Praxis, 2003
“Russia's Cosmonauts - Inside the Yuri Gagarin Training Center”
by Rex D. Hall, David J. Shayler, Bert
Vis, Springer Praxis, 2005
毎日新聞 1988年9月7日 朝刊/夕刊