サバイバル(1)
 上空380キロに浮かび、地球を周回する「国際宇宙ステーション」(ISS)。蒼い地球を眼下に臨み、優雅に宇宙を航行するその姿は子供達に夢を与え、大人達に人間と宇宙の関わりを考えさせる場を提供しているというのは、大げさだろうか。
上空380キロに浮かび、地球を周回する「国際宇宙ステーション」(ISS)。蒼い地球を眼下に臨み、優雅に宇宙を航行するその姿は子供達に夢を与え、大人達に人間と宇宙の関わりを考えさせる場を提供しているというのは、大げさだろうか。
2000年のシャトル事故で建設が一時中止になっており、現在はロシアのロケットで交代要員や物資の輸送が行われているISS。米・露の活動が目立つが、これは日本を含む15ヶ国もの国が参加している国際プロジェクト。ただ、我が国独自の実験棟「きぼう」はとっくに完成し、米国へ運ばれているものの、まだ打ち上げられていない。
ISS全体の最終的な完成は2010年頃に設定されており、その時、上の写真よりもより壮大な姿が出現することになっている。
冷戦崩壊から10年以上経ち、一般には“米ロ協力”自体への新鮮みは無くなりつつある。だがこのISSの本格建設にこぎ着けるまでの道のりは困難を極め、「悪夢」と呼ぶに相応しい。しかもそれは、両国の宇宙飛行士達が直接体験した、生死をかけたサバイバル。そこには、政府の思惑に翻弄された男たちの辛い物語がある。今回から数回にわけて、宇宙ステーションを舞台にした彼らの闘いをご紹介しよう。
◇
米航空宇宙局(NASA)は1969年から3年間、アポロ計画を完遂させたが、その後、さしあたって明確なビジョンを持たなかった。そもそも月着陸だけを目指して突っ走ってきたのであったから当然といえる。アポロ後のNASAに対する政府の風当たりは強くなり、サターンロケットを改造した「スカイラブ」を打ち上げ、宇宙ステーション“もどき”の事をやったものの、短期で打ち切られ、その後はシャトルの開発に専念することになった。
「再利用可能は低コストを実現し、商業衛星の打ち上げや宇宙基地建設の資材運搬に最適」と謳われた…いや、謳ったNASAは、それに全てを賭けたのだった。ただ勿論、冷戦時代、宇宙開発は敵国・ソ連との重要な競争ファクターであったため、政府も完全無視したわけではなかったが。
一方の旧ソ連はどうであったか?彼らは“ムーン・レース”の敗北を悟ると、さっさと方向転換を図り、宇宙長期滞在に意義を見出そうとした。長期居住に耐える宇宙船「サリュート」を建造し、長期滞在記録を次々と塗り替えていった。これらは地味ではあったが、確実にノウハウを蓄積していった。
ソ連はやがて、同盟国の人間もサリュートに搭乗させるようになった。モスクワへ赴き、そこで好待遇を受け、“宇宙旅行”を体験させてもらい、母国へ帰る…ゲスト達は皆、帰国後にソ連の“良さ”を熱く語っていたという。プロパガンダとしての宇宙の利用法は、ソ連はうまかったと言えるかもしれない。
◇
ソ連は1970年代後半になると、それまでのサリュートを卒業し、次世代型の本格宇宙ステーション建造を目指した。1976年2月の共産党中央委員会で正式にゴーサインが出されている。新型ステーションはそれまでのサリュートと異なり、複数のドッキングポートを備え、区画の増設、つまり“建物の増築”が容易になっている仕様であった。
このステーションの核というべき、乗員が寝食を行う「居住区画」(コア・モジュールという)が1986年2月20日に打ち上げられた。これには同年に開かれる共産党大会に花を添える意味があり、つけられた名前を「ミール」という。
ミールはロシア語で「平和」の意。当時、米国のレーガン大統領は対ソ強攻策をエスカレートさせ、両国のテンションは高ぶっていた。ミールの名は、米国の態度に対する当て付けであったという。しかもこの1ヶ月前、米のスペースシャトル・チャレンジャーが爆発事故を起こしている。この惨事が、相対的にソ連の優秀さをアピールする形になったのは、偶然とはいえ皮肉である。
「米国は宇宙長期滞在に興味はなかったのか…?」 決してそういう訳ではなかった。1982年、レーガン政権は西側各国が共同で宇宙ステーションを建造する提案を出し、日本を含めた10ヶ国以上が賛同していたのだ。それは88年に「フリーダム」という名が与えられ、開発は本格段階に移行しようとしていた。
だが、その後の両国は大問題に襲われる。それは戦争ではなく、経済の問題だった。
◇
 ソ連経済は1980年の初頭、既に破綻していたという説がある。事実、70年代後半から生産は停滞し、しかも東側同盟国は我慢の限界に達しつつあった。そんな祖国の復活を賭け、時代が選んだ男は若き獅子、ミハイル・ゴルバチョフ(写真)だった。
ソ連経済は1980年の初頭、既に破綻していたという説がある。事実、70年代後半から生産は停滞し、しかも東側同盟国は我慢の限界に達しつつあった。そんな祖国の復活を賭け、時代が選んだ男は若き獅子、ミハイル・ゴルバチョフ(写真)だった。
「この男は優しい顔をしているが、白い歯は鋼鉄でできている」
ゴルバチョフを選出した党中央委員会議長は、そう太鼓判を押した。そしてそれは、事実だった。彼は共産主義を保ちつつ、市場経済を取り入れるという前代未聞のやり方を選び、かつ、情報公開を進めた。「ペレストロイカ」と言われたそれはそもそも、国の内情を民衆に知らしめることによって、国民の目を覚まさせるというのが本来の目的であったという。
ただ、その荒治療の結果は、歴史に刻まれた通りである。あらゆる部門に否応なく組み込まれた市場経済はロシア人には理解不能。資本主義では当たり前の「保険金」の意味すらよくわからなかったものが殆どの中、結局中途半端な自由経済は負のスパイラルに陥り、それは宇宙開発も例外ではなかった。
宇宙飛行士達は、宇宙へ飛ぶことを始めとして、ミールで行われる実験や各種作業といったもの全てを細かく査定されることになった。「ドッキングがうまくいかなかったら」「宇宙遊泳を行ったら」「実験を遂行したら」等々、どれも採点対象になった。彼らにはまず、ロケットに乗って宇宙へいくというだけでボーナスが出た。いわば“出張費”である。
それまで飛行士達は、命令さえすれば即座に動く人間だった。しかしこの頃から、予定外の修理活動などにもボーナスを払わねばならなくなり、飛行士側も「いくら手当がつくのだ?」等と露骨に意識するようになった。市場経済がもたらした負の側面が、皆を苦しませようとしていた。
宇宙飛行士で、カネを口にするものは元々いなかった。彼らは確かに好待遇であったが、情熱は威信を背負った、本物のヒロイズム。宇宙を飛ぶためには、死を恐れない連中だった。それ故、国民は飛行士達を英雄視し、心の底から拍手を贈っていたのだ。だが、飛行士達が給料を意識し始めたその時から、国民の心は離れていった。大々的に報道される彼らの活躍にも、「それがどうした?」…民衆は冷笑するだけになった。
 予算の不足は、設備の保守にも影響を与え始めていた。老朽化が進んでも、取り替えることができない。設備の更新も難しい状況だった…いやそれ以前に、職員や技術者達に払われる給料自体がなかった。飛行士らはまだよい方で、一般職員への給与は滞るのが普通だった。
予算の不足は、設備の保守にも影響を与え始めていた。老朽化が進んでも、取り替えることができない。設備の更新も難しい状況だった…いやそれ以前に、職員や技術者達に払われる給料自体がなかった。飛行士らはまだよい方で、一般職員への給与は滞るのが普通だった。
写真はモスクワの飛行管制センター(ツープという)である。職員がちらほら見えるが、非番の時は通訳やタクシー運転手のアルバイトをする者も多いという。
大画面の下に並ぶ企業の看板が印象的である。
◇
89年頃から、ソ連の宇宙ビジネスはより過激になった。ミールへ一般人を乗せてやる、と言いだした。勿論、タダではない。これに飛びついたのが日本のテレビ局で、1990年、1人のジャーナリストを送り込んだのは世界でも大きく取り上げられた(写真右下、TBS・秋山氏)。彼はしかし、正式な飛行士ではなく、また、“旅行”という訳でもないため、未だその飛行に対するポジションは曖昧なままだ。この飛行でソ連には、1200万ドルが支払われたという。
 蛇足だが、このイベントでは、彼が乗ったソユーズロケットの打ち上げが生中継された。それを見ていた私には、日本人が宇宙船に乗って宇宙へ向かおうとしていることよりも、ロケットに描かれた“広告”が衝撃だった。ロケット上段には「大塚製薬」「SONY」「ユニチャーム」の文字がはっきりとペイントされていた。かつてなら、ソビエト連邦を意味する「CCCP」の文字であったろう。
蛇足だが、このイベントでは、彼が乗ったソユーズロケットの打ち上げが生中継された。それを見ていた私には、日本人が宇宙船に乗って宇宙へ向かおうとしていることよりも、ロケットに描かれた“広告”が衝撃だった。ロケット上段には「大塚製薬」「SONY」「ユニチャーム」の文字がはっきりとペイントされていた。かつてなら、ソビエト連邦を意味する「CCCP」の文字であったろう。
特番では誰もコメントしなかったが、最も重要で、最も本質的な変化とは、正にそれではなかったか。
◇
1991年12月、ゴルバチョフは国家の解体を宣言した。鋼鉄の歯とはいえ、もはや立て直しは不可能だったのだ。ここに、革命以来70余年続いたソビエト連邦が崩壊したのだが、程なく「ミールを丸ごと売るのではないか」という噂が流れ、7億ドルの値が付くかもしれないという試算まで飛び出した。
これを聞いて苛立ったのは、ミールに搭乗していた飛行士達だった。
「ミールを売るというのは本当か?それで聞きたいのだが … 売るのは俺たちも一緒か?」
ミールの身売りは結局無かったが、宇宙を利用したビジネスが衰えることも無かった。ある時はペプシのポスター撮影が行われた。またある時は、ミールを舞台にした映画の撮影も提案された。結局、映画は実現しなかったが、他に向けてロシア当局が資金集めに奔走したのは間違いなかった。一時は、即刻現金を注入しなければ、冗談抜きで破綻するという寸前にまで追いつめられた。宇宙当局が欲しかったのは今や栄誉ではなく、現金だった。ミールの更なる進化形である「ミール2」計画もあったが、その実現はもはや、夢物語だった。
◇
ところで。宇宙開発に関しては比較的潤沢な資金が得られているであろう米NASAも、80年代終わりから苦しい立場を歩み始めていた。日本はバブルの絶頂を迎えつつあったが、米国では景気後退が鮮明化し、連邦予算自体の緊縮が叫ばれつつあったのだ。アポロ以降、魅力あるビジョンをいまいち打ち出せないでいるNASAは当然ながら矢面に立たされた。シャトルの飛行は再開していたが、そもそも何のために飛ぶのか、はっきりしなかった。
「“新しい資料実験を行う!”と主張しているが、その成果をはっきり見た例しがない。論文を見たことがない!」
と鋭い指摘をする者もいたが、確かにその通りだった。因みにこれは、NASAだけではなかった。そもそも、“巨大科学”自体が受難の時代を迎えつつあった。例えば素粒子を調べるためにテキサスで建設中の、空前の超巨大加速器の行く末も、議会を2分して大揺れだったのだ(結局、93年に建設中止)。
「米国では社会的目標の少ない純粋科学に重きが置かれ、社会的要請へ応える分野への予算配分が少ない」と主張する者もいる状況で、宇宙ステーション「フリーダム」の建設も、前途が危うい状態が続いていた。レーガンが提唱してから7年間に80億ドルも費やしたのに、まだ1つも建造物が打ち上がっていなかったのだ。反対派は一刻も早くつぶすことに執念を燃やしていた。
◇
さて、米国とロシアが手を組むことになったのは、なぜなのか?
その源流は、現大統領の父、ジョージ・ブッシュ大統領にある。しかも、全く政治的な都合が根底にはあった。
彼がひどく気にしていたのは、選挙だった。湾岸戦争で勝利したものの、経済問題が進展せず、支持率は急速に低下し、何としてもポイントが欲しかった。世論調査では、クリントンと五分という数字が出ており、ピンチだった。1992年6月、ロシアの新大統領ボリス・エリツィンがワシントンへ会談に来る予定になっていたが、それは点数稼ぎに好都合だった。だが…メインに据える、面白みのある議題が何一つなかったのだ。
NASA上層部はこれをチャンスとつけ込み、ホワイトハウスに接触、かなりいやらしい手法で会談4日前に議題としてねじ込むことに成功した。そもそも宇宙飛行士の交換というアイディアは、先年交わされたゴルバチョフとの会談で既に扱われていたのだったが、ソ連のその後の混乱で頓挫した。それを復活させようというのである。
だが、ブッシュは結局ホワイトハウスを去り、クリントン政権が誕生することになる。この新政権もやはり、フリーダムには冷ややかだった。新たな予算局長はなんとしても計画を葬り去ろうとし、NASA上層部は何とか回避しようと必死だった。
ところが、1つの外交問題がNASAに追い風となった。ロシアがまだソ連だった1990年、同国がインドへロケットエンジンを売るという秘密協定に合意、これが明らかになって以降、米政府はロシアに対し、この協定を放棄するように迫っていたのだった。
インドがロケットエンジンを手に入れれば、それで核弾頭搭載の弾道ミサイルを実現しかねない。そうすれば隣国・パキスタンも同様の事を行うはずで、南アジアの軍事的緊張がエスカレートしかねないというのが米の懸念だった。
92年4月、発足したばかりのクリントン政権はついに、エンジン販売の“正規代理店”であったロシア宇宙総局に制裁を加えることを決定、強硬手段に出た。
ロシアの目的は1つである。現金が欲しかったのだ。ピンチに陥った彼らだったが、NASAが宇宙飛行士交換計画を復活させようとしている情報を手に入れると、ひらめきは早かった。NASAと手を組み、宇宙ステーションの建設費プラスアルファをひったくろうと目論んだのだ。ステーション建設は長期に渡る“安定収入”を意味する。危険なリスクを冒した、その場限りのエンジン販売より遙かにうま味がある。
「ロシアがアメリカに協力して国際宇宙ステーションを作るのはどうか?」
ロシア側のこの提案に、米政府とNASAは乗った。「ロシアはエンジン販売をやめる。それに、ロシアは長期宇宙滞在へのノウハウを持っている。米ロが協力すれば、ステーションは安くできる。クリントン政権の外交力に、大きなポイントにもなる」と。
この時点で米国は、自分たちが実は“乗せられた”ことに気付いていない。
 こうして、今日の国際宇宙ステーション・ISSの原形ができあがった。まず、ロシアが保有しているステーション「ミール」に米国人飛行士が長期滞在し、そのノウハウを学ぶ。その後、この経験を生かしてISSの建設を開始する。ミールへの米国人の移乗は、シャトルがミールにドッキングすることで行われる、というものだった(写真・95年6月の初ドック)。
こうして、今日の国際宇宙ステーション・ISSの原形ができあがった。まず、ロシアが保有しているステーション「ミール」に米国人飛行士が長期滞在し、そのノウハウを学ぶ。その後、この経験を生かしてISSの建設を開始する。ミールへの米国人の移乗は、シャトルがミールにドッキングすることで行われる、というものだった(写真・95年6月の初ドック)。
ところが、これらはホワイトハウス及びNASA上級幹部達が思惑だけで決めたことであった。NASAの現場の意見は全く無視されていた故、彼らは冷ややかだった。むしろ無関心だったとも言える。
ミールに乗るためにはモスクワへ行って訓練を受けなければならなかったが、誰も行きたがるものはいなかった。飛行士の中にも、志願する者は殆どいなかった。自分のスキルを磨くため、もう一度宇宙を飛びたいためといった特別な想いや事情を抱えた者が、僅かにいただけだった。行かされるハメになった者もいる。
「シャトル・ミールミッションって、なんだい?」
計画そのものを知らない者さえいた。
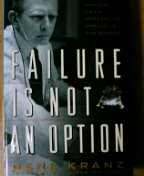 ただ、正面切って反対する者も勿論いた。ミールや、ロシアの宇宙開発そのものの安全性を指摘する者もいた。その例はフライトディレクター、ジーン・クランツだ。彼は伝説のフライト・ディレクターで、映画『アポロ13』でエド・ハリスが演じた役と言えばわかりやすい。彼は懸念を表明し反対したが、脇へ動かされたのは彼の方だった!
ただ、正面切って反対する者も勿論いた。ミールや、ロシアの宇宙開発そのものの安全性を指摘する者もいた。その例はフライトディレクター、ジーン・クランツだ。彼は伝説のフライト・ディレクターで、映画『アポロ13』でエド・ハリスが演じた役と言えばわかりやすい。彼は懸念を表明し反対したが、脇へ動かされたのは彼の方だった!
(写真・クランツ氏の現役時代を振り返った回顧録 かなり読み応えあります!)
◇
計画が具体的に動き出した。表面上は国際協力、しかも冷戦集結の象徴としてチヤホヤされたが、実情はそんな甘いものではなかった。それは、文化と文化の衝突だった。
ロシアではチームワークと自己犠牲が重視されていた。勿論、集団主義に起因するものであったが、それは米国人の個人主義とは真っ向から衝突した。次号で登場する米国人飛行士リネンジャーは、中でも特に個性の強い男で、何かあるたびにロシア人と衝突した。一方のロシア人達は裏で、ワガママな米国人をウォッカのつまみにしては、散々こき下ろしていた。
宇宙飛行士の管理や選定にも大きなずれがあった。ロシアでは昔から医学・心理学者が大きな幅を効かせている。米の基準ではOKの飛行士でも、ロシアの医師団がノーと言うこともしばしばだった。先のリネンジャーなど、自身が医者であるから衝突は激しかった。審査の最後にある健康診査の結果にも正面から反論した。「全く無意味だ」と。実際、ロシアの医療知識も設備も、それほど高度という訳ではなかった。
それまで、ロシアの医師団が飛行士達から反論を食らったことは無かった。それほど強い権力を持つ医者達だったため、この“反撃”にかなり困惑し、苛ついたのは間違いなかった。
一方、ロシア宇宙開発の現場で特有な存在に、心理学者がある。狭い空間に人間が長期に渡って閉じこめられる事への研究は、かなり進んでいた。しかし米国人はそれを直ぐに認めようとしなかった。そもそもロシア人が心理にうるさいのは、かつて飛行士同士の軋轢が原因で打ち切らねばならなかったミッションがあるからだった。当然だが、彼らの権力も強かった。
安全性に関する認識も大きくずれていた。米国の場合、例えばドッキングの失敗など、重大な事態が発生すれば地上に帰還するのが普通だったが、ロシア人なら宇宙服を着込んで船外へ飛び出し、手探りで修理しようとする。そもそもミール自体、米の基準からすれば即廃棄となるような状態にあった。それを、修理しながら飛ばしていたのである。
そして、決定的な壁は、言語だった。
ロシア語が話せる米国人はそういない。飛行士達も数ヶ月の特訓で身につけた程度。仮に傍でロシア人達が悪口を言っていてもわからなかっただろうし、それが俗語であればなおさらである。勿論それはロシア人も裏返して同じだった。
1995年6月、スペースシャトルがミールに初のドッキングを果たした(上写真)。この後、度々シャトルが訪問するが、得るものは混乱ばかりだった。それが1997年、ピークを迎える。
【Reference】 どの資料も詳しくわかりやすく、推薦です!
“Star-Crossed Orbits”by James Oberg, McGraw-Hill, 2002
「ドラゴンフライ」(上)(下)ブライアン・バロウ 著 小林等 訳, 筑摩書房,
2000 (かなりオススメ!)
S.P. Korolev Rocket and Space corporation Energia http://www.energia.ru/english/index.html
NASA Human Spaceflight http://spaceflight.nasa.gov/home/index.html