���͒n���ɋA���Ă���
�\�A���F����Ԃ֑ł��グ����������Ƃ��Č���I��ł������ƁA�����Ă��̋L�O���ׂ���P�����u���C�J�v�ł��������Ƃ͊��ɐG�ꂽ�i�u�X�y�[�X�E�h�b�O�v�A�u�`���̌��E���C�J�v�j�B����������܂ŁA�䂪���ɂ����铖���̕ɐG�ꂽ���Ƃ͑S���Ȃ������B
�u���E���ő呛���ɂȂ����v�Ƃ悭�����邪�A�ł͓��{�ł͉ʂ����āA�ǂ̂悤�ȕ��Ȃ���Ă����̂��낤�B���킹�āu���C�J�v�����āu�N�h�����t�J�v�Ƃ��������ǂ̎��_�Ō��ɂȂ�A��ʉ����Ă������̂��A���߂ĒH���Ă݂����c�M�҂͂��̂悤�Ȍl�I��������A�}���ق���A�����̐V����H���Ă݂��B�����ł͂������ē���ꂽ��������ɁA�X�v�[�g�j�N�Q���ɑ��郁�f�B�A�̔����ƕ��e�̐^�U�A���̔w�i���Ղ��Ă݂����B
��
�\�A�ł̓X�v�[�g�j�N�P���̑ł��グ�i�P�X�T�V�N�P�O���S���j�ȑO����A�F���֔�ї������Ƃ��Č����I��A�P�����������Ă������Ƃ͂悭�m���Ă���B�\�A�͂��̂��Ƃ��A�ʐ^�������Ď��X�Ă����B����͓��{�ł��Љ��Ă���A�ȉ��͂��̈��ł���B
| �@�@�F�����s�͌�����ԏ���@�l�H�q�������̉A�̗E�m �@�@�����P�Ŕ�яo���@ �@�@�@�@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�F�{�����V�� ���a�R�Q�N�i�P�X�T�V�N�j�P�O���Q�O���i���j�����@�U�ʁz |
���̋L���͎q�������ɏ����ꂽ���̂Ō��o���ɂ��t���K�i���U���Ă��邪�A���e�͑�l���ǂ�ł��[�����ɂȂ�A���ɖ����ȋL�����B�ʐ^�̌��E�A���r�[�i�̓L���v�V�������u�A���r�[�i�N�v�ƂȂ��Ă��邪�A�{���́u�A���r�[�i��v�B�A���r�[�i�̓��C�J�̃o�b�N�A�b�v�h�b�O�ł���A�������������炪�L�͌��ł��������A�u�݂�Ȃ̐l�C�҂ł��������Ɓv�A�u�ŋߕ�e�ɂȂ������ƂŎq���̂��߂ɕK�v�ł��邱�Ɓv�𗝗R�ɊO���ꂽ�̂ł������i�u�`���̌��E���C�J�v���Q�Ɓj�B
���āA�P�O���Q�X���t�����ʂɂ́A���ɏ������Ȃ�������ڂ��ׂ��L��������B
| �@ �\�A�A�l�H�q���̊ϑ��ŗv���@�p�Ȋw�҂� �i�W���h�����E�o���N���p������\�������`�o�A�����j���E�ő�̓d�g�]���������W���h�����E�o���N�̉Ȋw�҂͓�\�����A���X�N���̃\�A�V���w���l�H�q���̊ϑ��𑱂���悤�v�������d���������B���d�g�]�����̐ӔC�҃��[�x�������ɂ��A�\�A����̓d��͂Ƃ��ɓ�\�����̐l�H�q���ɒ��ӂ��ė~�����Əq�ׂĂ���A�������͒����Ɋϑ����J�n���A�q���������\�������ł��郍�P�b�g�]�����Ŋm�F�����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�F�{�����V�� ���a�R�Q�N�i�P�X�T�V�N�j�P�O���Q�X���i�j�����@�Q�ʁz |
�W���h�����o���N�V���䂪�\�A�̐l�H�q����ǐՂ��Ă������Ƃ́A���T�C�g�̑��̘b�ł��������Љ���B�\�A������f���T���@��ł��グ�A���̎��ɓ��V����ɒǐՂ��˗����Ă������e���������A���̂悤�Ȉ˗��̂��������������ɂ������킯���B
�����āA�^���̂P�P���S�����}����B
| �@�@ �����悹���l�H�q���@��� �@�@�@������Ԃ�����@�O��̘Z�{�@�d���͌ܕS�` �i���X�N�������O���`�b�g�A�����j�\�A�̃^�X�ʐM�́A�\�A���O���l�H�q�����ł��グ���Ɣ��\�����B�i�ꕔ����j ��A�l�H�q����͎O���ߑO������\���Ɠ��㎞�ܕ��i���{���ԓ����ߌ�ꎞ��\���ƌߌ�O���ܕ��j�̓�X�N������ʉ߂���B ��A����̉q���ł��グ�Ɗe��̉Ȋw�@�B�A���������̐ύڂɂ���āA�F����ԂƏ�w��C���̌����͈�i�Ɛ[�܂�A�l�ނ͂��������F���̐_��ɋ߂Â����ƂɂȂ�B ��A����̔��˂͊v���l�\���N���L�O������̂ł���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�@��ܕS�`�̏�����@ �O���ߑO�����l�\�ܕ��i���{���ԓ����ߌ�l�\�ܕ��j���X�N�������Վ��j���[�X�ɂ��A�^�X�ʐM�͓����\�A���l�H�q����ł��グ�ɐ��������Ƒ�v���̂悤�ɔ��\�����B ��A�\�ꌎ�O���l�H�q����̑ł��グ���s�����B ��A�l�H�q����͐��i���P�b�g�̍ŏI�����ł���A�Ȋw�������߂Ă���B ��A�l�H�q���ɂ́A���z���������A�F���������A���x�ƋC���ׂ��B�A�����p�����i���j����ꂽ���e��Ɨ\���H�ƁA�F����Ԃɂ����邻�̐�����Ԃׂ鏝�A����ђn��֊ϑ������𑗂鑕�u�����߂Ă���B ��A�l�H�q������̓d�g���M�͔g���l���E������ѓE�����܃��K�T�C�N���i���E�܂���я\�܇b�j�ɂ���čs����B ��A�l�H�q���̑��d�ʂ͌܁����E�O�`�ł���B ��A�l�H�q���̋O�����x�͕b����b�ł���B ��A�l�H�q���̒n�ォ��̍ő勗���i���n�_�j�͈��ܕS�`�A�����͖�ꎞ�Ԏl�\�A�ԓ��ʂɑ���X���p�͘Z�\�ܓx�ł���B ��A�l�H�q���̔�����ϑ������ɂ��A�Ȋw�@�B�̊����Ɠ����̐�����Ԃ͋ɂ߂Đ���ł���B ��A�E�����܃��K�T�C�N���̓d�g���M�͎����A�x�~�Ƃ��Z�E�O�b�Ԋu�̔��M�M���A�l���E�����K�T�C�N���̕��͘A���ŋx�~�����ł���i�`�b�g�������j �@�@���ւ̔��˂����ɂł��\�@�p���Ƃ����� �i�����h���O�������C�^�[�A�����j�\�A�̑��l�H�q���ł��グ�ɂ��āA�p���F�����s����̃P�l�X�E�K�g�����h����͎O���u����̓\�A���A���Ȃ�̑傫���̕��̂�ς��P�b�g�������ɂ����Ɍ����Ĕ��˂ł��邱�Ƃ����������̂��v�Əq�ׁA����Ɏ��̂悤�Ɍ�����B ��q����ł��o�������P�b�g�̏d���͏��Ȃ��Ƃ��ܕS�d�͂������͂����B���̐���́A��|���h�̕��̂��^�Ԃ��߂ɂ͈��|���h�̏d���̃��P�b�g���K�v���Ƃ̒���������Ƃ������̂ł���B�\�A�������V�������w�R���Ȃ茴�q�͐��i��������肾�����̂ł͂Ȃ�����A���̐���͌���Ă��Ȃ��͂����B �@�@���͉F���̒�@���@����Ă���̂́g�����_�h�@ �\�A�̐l�H�q����ɂ̓����N������Ă���B���̃����N�A�\���H�Ƃ܂Ŏ����Ắg�F�����s�m�n�P�h�ɂȂ������A���͐l�Ԃ��F�����s�ɂł������@�W�ł�����B�\�A�͓��������w�ɏグ�āA���w��C���ł̓���Ȑ������ۂ̊ϑ���Z�N�O�̈��܈�N����͂��߂Ă����B�͂��߂̓������b�g��T���Ȃǂ��̂��Ă������A���܂ł͗����Ȍ����g���Ă���B�g�R�W���c�J�h �g�����_�h �g�}���C�V�J�h �Ȃǂ̌��̓��P�b�g��s�̃x�e�����Ƃ��Ēm���A��q���ɂ́g�����_�h������Ă���Ƃ݂��Ă���B�\�A�̍ŋ߂̊w����𑍍�����ƁA����l�H�q���ɏ悹�Ă���ړI�́A ��A�������X�s�[�h�őł��������鎞�������ǂꂾ���̉����x�ɑς����邩�B ��A�n���̈��͂����Ȃ��Ȃ����Ƃ����A�Ȃ��Ȃ����Ƃ���œ����͂ǂ�Ȑ������ۂ������邩�B ��A���w�̌��������x�̕ω���F�����̒��łǂ�ȕω����邩�B �̎O�ɂȂ�B��s�@����яo������}�~������ꍇ�A�傫�ȉ����x�������A�ڂ�����ނ��Ƃ�����B��������X�s�[�h�̑������P�b�g�ɏ�������A�����͂ǂ�Ȃ��ƂɂȂ邩�A�ǂ�Ȏ����ɂ���Ώ���Ă��铮���ɊQ��^���Ȃ������ő�̖ړI���B���͂̂Ȃ���Ԃ�n��ɍ�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B������l�H�q���ɓ������悹�Ă��̏�Ԃɂ����A����܂ł킩��Ȃ����������̖�肪���ׂ���B�Ⴆ�Ό��t�͕��ʂɏz����̂��A�S���̌ۓ��ɕω��������邩�A�����邩�A�H�Ƃ␅���Ƃ邱�Ƃ��ł��邩�c�A���܂܂őS�����m�̐��E���B���w�ɏ��Η뉺�Z�A���\�x�ɂ�������Ƃ��낪���邵�A�F��������̂悤�ɍ~�蒍���w������B�������ǂ����Έ��S���A�܂��F�����̉e�����ǂ��o�邩�B�l�ނ��F���ɏo�閲�ƂƂ��ɁA�����̉𖾂ɂ��𗧂B �\�A�̐����w�͐��E�̍ō���Ƃ���Ă���A�܂��p�u���t���m�̏������˂��炢��������ɓo�ꂷ��B����̓T��������b�g�����l�Ԃɋ߂������������Ă��邱�ƁA�T���͐�����Ԃň��łȂ����ƁA�܂��g���������Ƃ����R�Ƃ��Ă�������B���͓��ʂ̌P�����قǂ����Ă��邪�A���܂܂ł̎������@�͓�ʂ肠��悤���B��͒n��Ɠ����C���̋C�����̒��ɖ������������Ɍ�����ꐂ���ɕS�\�`�ł��������B�������烍�P�b�g����Ƃ��p���V���[�g�ɂ��āA�O���Ԃ����Ă�����艺�낵���B���͖��͂��ƌċz�ɕω����݂�ꂽ�����ő��͐��킾�����B�����ЂƂ̕��@�́A�C�����͂Ȃ��Č��Ɏ_�f�z����̂������w����s���𒅂��Ĕ�����B���x�S�\�`�Ō�����������Ă��镔��������������ė����n�߁A�O�b��Ƀp���V���[�g���J���Ė�ꎞ�Ԃ������Ēn��ɍ~��Ă������������͂��ƌċz�Ɏ�ُ̈킪�݂�ꂽ�����Ō������͌��C�������Ƃ����B �@�@��O���P�b�g���q���@��B�̕ی�ɖ𗧂� �\�A�͎O���A�l�H�q����̑ł������ɐ��������Ɣ��\�����B�\�A���\�ꌎ�����̃��V�A�v���l�\���N���L�O���đ��ł�������Ƃ������Ƃ͂��˂Ă���`�����Ă���A���E�e�n�̊ϑ��w���ܓ�����ϑ����n�߂邱�ƂɂȂ��Ă������A���̗\�z���O�����������킯�ł���B ��̓����͉��Ƃ����Ă��ڕ����܁����E�O�`�����邱�Ƃ��B��P���͔��O�E�Z�`���������A����ł��č��̗\�肵�Ă���\�`�ɂ��̂ɔ�ׂĂ���߂đ傫�����Ƃ����E�������������A����͂���ɂ��̘Z�{�ł���B �ܕS�L���̕��̂�b�����`�Ŕ�����Ƃ̂ł��郍�P�b�g�Ȃ�A���d�̐������^�ѓ�����̂Ɛ��肳���B�]���ă\�A�͂��łɒn����̂ǂ��ɂł������𓊉��ł���悤�ȑ嗤�Ԓe���e�i�h�b�a�l�j�������Ă�����̂ƍl������킯�ł���B �i�����j ����ɍ��x�̑�͑�O�i�ڂ̃��P�b�g�����̂܂ܐl�H�q���ƂȂ��Ă��邱�Ƃ���̓����ł���B����͒��ɏ悹�Ă��錢��A�@�B�ނ�ی삷��ɖ𗧂��낤�B�i�ȉ����j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�F�{�����V�� ���a�R�Q�N�i�P�X�T�V�N�j�P�P���S���i���j�����@��ʁz |
�S�������͈�ʂŁA�X�v�[�g�j�N�Q���̑ł��グ���X�I�ɕĂ���B�ȑO����\������Ă������̂ł͂��������A�����m���ɍڂ��Ă��邱�Ƃ����ڂ��W�߂Ă���B�X�v�[�g�j�N�P���̑ł��グ�̎������i�u�X�v�[�g�j�N�̎v���o�v�Q�Ɓj�A���ʂ���`��鋻�������肠��Ƃ��Ă���悤�Ɋ�������B
�������������A���̎��_�œ��ɒ��ڂ���Ă���̂́A���̏d�ʂ��B�q���̏d���͂T�O�O�������ƂȂ�A����̓X�v�[�g�j�N�P�����U�{������B�č����P�O������������̉q�����O���ɑł�������̂Ɏl�ꔪ�ꂵ�Ă���Œ��A�\�A�͂T�O�O�����̕��̂��y�X�Ǝ���O���ɏグ���̂��B�������A�������̕s���̑ł��グ���P�b�g�ɁA�����Ȃ�ʋ��Ђ������Ă���̂��悭�킩��B
���̎��_�łǂ̌����g��ꂽ�̂��܂����Ă��Ȃ����A����Łu�����_�v�Ƃ���Ă���̂������[���B�܂��A�q���Ƒ�R�i���P�b�g����̉����Ĕ�s���Ă��邱�Ƃ��\�A�͂͂�����ƕ\�����Ă���B�Ȃ��A�d�g�͓��{�e�n�ł���M����A�P���̎��Ɠ������̂��Ƃ�����ۂ�N���������Ă���B
�����āA�P���̎��ƌ���I�ɈႤ�̂́A���̑ł��グ�ɐ����I�Ӗ����͂�����Ǝ����������Ƃ��B�^�X�����̍s�ɂ���A�u����̔��˂͊v���l�\���N���L�O������̂ł���B�v���F�ʂ�����Ă���ƌ����邾�낤�B�\�A���{�ɂƂ��Ă��܂�l�H�q���͂�������ł͂Ȃ��A�����̓���Ƃ��ăg�b�v�Ɉʒu�t�����u�Ԃł������B
���̓��̗[����ʂ́A����w�A�q���̘b��œ�����Ă���B��錩�o����������̋������A�ǂݎ����藧�Ă�B�����Ă����ŏ��߂āA�u�X�v�[�g�j�N�v�A�u���C�J�v�A�u�N�h�����t�J�v�Ƃ������t���o�ꂷ��B
| �@�@�l�C�J��グ���ˁ@�\�A�̑��l�H�q�� �i�����h���O�������������h���j�W���[�R�t�����̒Ǖ���ǂ�������悤�ɑ��̐l�H�q�������˂��ꂽ�̂��@��ɁA�����ʐM�����h���x�ǂ̓��X�N���̎���x�ǒ����O���ߑO�\�ꎞ�i���{���ԓ����ߌ㔪���j���ۓd�b�ɌĂяo���āA�����������X�N���̕\����Ă݂��B�ȉ��̓��X�N���Ƃ̈��ꓚ�B �@�@�@�@�@�@�@  �@�@�Y���ꂽ�W���[�R�t�Ǖ��@�����ɕ������X�N�� �������h���@�W���[�R�t�̒Ǖ��͗\�z�ʂ肾�������A���̐l�H�q���̕��͈ӊO�ɑ����������������A���̂��i����j���炫�傤�i�O���j�ɂ����Ẵ��X�N���̕\��͂ǂ����B �����X�N���@�����̃��X�N���͐l�H�q���̘b�Ŏ������肾�B�W���[�R�t�̖��Ȃ܂�ŖY�ꂽ�`�ŁA��A���O�̘b�̂悤�Ȋ������B�W���[�R�t�̔��\���������͓̂����̏\�����̃��W�I���������A���̎��͂�������ꂪ���傤�̘b�肾�Ƌ^��Ȃ������̂��A�����̘Z�������Ȃ茢��������傫�ȑ��̐l�H�q������яo�����Ƃ����̂ő呛���A���W�I�͂��̌���������������A���W�I�E�J�[�܂ŊX���������������ă��X�N���̎s���͈��̋�����Ԃ��B �������h���@����Ɋv���l�\���N���ԋ߂ɔ����āA���̂��͖ё������Ǝ�Ȃ���荞��ł��Ă��邪�A�ǂ�ȗl�q���������H �����X�N���@�ё�Ȃ͓���ߌ�O����\�����X�N���̔�s��ɂ������A��ςȊ��}�Ԃ肾�����B���������ɂƂ��ẮA�W���[�R�t���}���ɏo�Ă��Ȃ������̂ŁA���悢��Ǖ��m���ƍŌ�̌��ɂ߂����郁�h�ɂȂ����B �������h���@�l�H�q���͎����̊v���L�O�����O�ɔ��Ԃ������̂Ƃ�����ł͗\�z���Ă������A�W���[�R�t�Ǖ��̔��\�ƌ��т��Ĕ��Ԃ��}�����悤�Ȋ��������邪�ǂ����ˁB �����X�N���@������������ɂ��Ǝv���Ă������A�m���ɌJ��グ���˂̊���������ˁB�W���[�R�t�̒Ǖ��̓\�A�ɂƂ��Ă��������l�H�q�����҂����_����������Ɏ����Ă��܂����������������A���������ǂ̑���˂ł�����x���n���������Ƃ����Ƃ��낾�B�z�e���Ȃǂł������͐l�H�q���̘b����ŁA�W���[�R�t�̂��ƂȂǖY��Ă��܂����i�D�����A����ɂ͐G�ꂽ���Ȃ��C���������낤�B�܂��m���ɂ��̐l�H�q���̕����ʔ�������ˁB �������h���@�\�A�̍����̓W���[�R�t�̂��Ƃ��ǂ��v���Ă����̂��낤�B �����X�N���@�s���̊Ԃł̓W���[�R�t�͐����ɕ]�����ǂ����銄�ɍ����ł͂���قǍ��������Ă��Ȃ��Ƃ�����]�����������A�Ȃ�Ƃ����Ă�����j��~�����̑�ȌR�l�Ƃ��āA�܂����h�Ȑl���Ƃ��Ă̖��͂͑傫�������悤���B����Ȉ̂��l���܂����E���T�̂悤�ȂЂǂ��ڂɉ���Ƃ͂���܂��Ƃ������C��������ʂ̎s���̐S�̒�ɂ͂������悤���B�����炫�̂��̔��\�͂�͂�ӊO�Ƃ����������������A�����̖ڂ̓͂��ʂƂ���łȂɂ��������Ƃ����̂��{���̎s���̋C�������Ǝv���B �������h���@���ꂾ���ɂ��������Â��ʂ���C�ɐ�������Ė��邢��]�ƌւ�������Ɏ��߂�����K�v���������Ƃ����킯���ˁB���̈�T�Ԃ͑啪�������ĈÂ���������������������ˁB �����X�N���@�m���ɂ��̈�T�Ԃ͈Ò��͍��̏�ԂŒ����ς����J���Ă���̂��ǂ����킩��ʂ��A���~�N���̐����������������A���Y�������ƂɃ��[�S����j���[�X������͂��߁A�T���ɂ͂��т����[�u���^���]�n�͂Ȃ��Ȃ����B �������h���@���ꂩ��̌��ʂ��͂ǂ����B������ł͒����ς̕[���傫�����ꂽ���Ƃ��d�����ăt���V�`���t�����̈��萫���^���Ă��邪�B �����X�N���@�����ς̉�c����q���Ă��߂����Ƃ͎��������A�S���v�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��邵�A�W���[�R�t�̐V�C���������Ϗ��L�ǂœK���ȗ�p���ԂƔ��������ɂ߂Č��߂����ł͂Ȃ����B�i�ȉ����j �@�@�u�V�q���v�n�����P�Q���@�S�O���ň���A�玵�S�`������s�@���̏�Ԃ��ɂ߂ėǍD �i���X�N�������O���`�b�g�A�����j�l�H�q����̂��̌�̉^�s�͎��̒ʂ�B �i�����j ��A���ےn���ϑ��N�v��Ɋ�Â��A��͓��ɉF����s�Ɋւ��鐶����w��̏d�v�Ȉ�A�̖����������邪�A���̂��߉q���͖������ɓ����A���C�J��̌���C��ς�ł����āA����̑��u�ɂ���āA���̏d�v�Ȑ����@�\�����낭���邱�ƂɂȂ��Ă���B���Ԏ������͂̎����Ƃ���ɂ��ƁA���͔�s�̓�������߂ċC�y�ɂ��Ă���A���̈�ʓI��Ԃ͖������ׂ����̂ł���B�ډ������������̐�����Ԃɑ���c�_���������Ă���B �i�����j ��A�܂����̎����܂łɑ��q���̐��i���P�b�g�͒n�����l�S�l�\�Z�������B�i�����l�H�q���ɏ悹��ꂽ���C�J��̌��̓\�A�A�X�J���W�i�r�A�k���X�ђn�т̎Y�A�w�^�P�l���|�Z�܃Z���`�A�����ג����O�p���ŁA���͗����Ă���B���X�A�N�}�A�e���A�V�J�Ȃǂ̎��Ɏg���A�\�A�ɂ̓��V�A�A���V�x���A�A���V�x���A�A���V�A�E�t�B���̎l�킪����A������ƃG�X�L���[���Ɏ��Ă���j �@�@�F�����s���̃����������@�Ă͋s�҂��ƕ��S�@���^�����~�X�E���j�o�[�X�@ �F�����ɐg���������ܒn��������Ă���B�\�A�̃X�v�[�g�j�N�i�l�H�q���̃��V�A��j��ł��グ��\�����Ă������E���̐l�X���g��z�V�O�h��n�ōs���\�A�̔��\�ɂ͓x�̂��ꂽ�悤���B���V���g���������h�����p�����X�v�[�g�j�N��茢�̕��ɘb�肪�W�܂��Ă���Ƃ����B�V�����D���̕č��l�̓X�v�[�g�j�N���������ă}�g�j�N�i�}�g�͎G�팢���Ăԑ���j�Ƃ����V��������B����������ł́A�ĉp�̓������싦������s�҂��Ƃ����̂ŁA�g�O�����[�g��ʂ��čR�c�𑗂�h�Ƒ�ςȔ������B�\�A�����𗘗p���č���̐������ۂ��������n�߂��̂͘Z�N�O�̈��܈�N����ł���B�i����܂ł̓T��������b�g���g���Ă����j�\�A�q��w�������A�E�y�E�{�N���t�X�L�[���m�����̒��S�l���B �ŋ߂ł͂��Ƃ��\���\�Z���ɎO�C�̌����S�\�`�̍���ɑł��グ�p���V���[�g�ʼn��낵���B�\�A�ɂ͂����F�����s�p�ɌP�����ꂽ��\�l�ȏ�̌�������Ƃ�����B�����̌��͑啔���X�s�b�c�n�̃��C�J��̂悤�ł���B���̃��C�J��̓\�A�̃X�J���W�i�r�A�����̖k���̐X�ђn�тɎY���鏬���Ȃ�傤����œ��͍ג����A�O�p���Ŕ��͗����Ă���B�Ƃ���ŋ������䂭�͉̂F�����s�p�ɑI�ꂽ�̂��݂ȃ��X���Ƃ������Ƃ��B����́u�ڕ����y���ČǓƂɑς�����v�Ƃ��������{���̐��i�i�H�j��ꂽ���̂ŁA�ŏ��̌����E�����҂͏������Ƃ����\�A�w�҂̈ӌ��Ƃ������Ă���B ���Ă���ǂ̃X�v�[�g�j�N�ɏ����h�ɗ������͓̂�\���C�̂����ǂꂾ�낤�B�\�A�̃u���S�k���z�t���m�͌��̖����g�N�h�����t�J�h�i������т̏��j�Ƃ����Ă���B�t�����X���Y�}�@�֎��́g�_���J�h�i�����ȋM�w�l�j�C�^���A���Y�}�@�֎��́g�����_�h�i���̖��O�j�ƃ}�`�}�`���B���邢�͓�A�O�̌���胍�P�b�g���ɑł��グ�A���̈�����������̂ŁA����Ȃɖ��O���H���Ⴄ�̂��낤�Ƃ����悤�Ȍ���������B������ɂ���ޏ��͐��^�����̏���u�~�X�E���j�o�[�X�i�F���j�v�ƂȂ����킯���B ���{���Ԏl���ߌ���݂ŃX�v�[�g�j�N�͎���n����������B�g���̈�ʓI��Ԃ͖������ׂ����́h�i���X�N�������j���Ƃ����B���̎��Ԃ�u���ĉq�����̃x������A���̂��тɐl�H�H�Ƃ��p�N���Ȃ��牺�E�����Ƃ����Ă�̂�������Ȃ��B�i�x���ƐH���̊W�͗L���ȃ\�A�̐����w�҃p�u���t�̏������˂𗘗p��������̂��̂ł���j�Ō�ɂ��̃~�X�E���j�o�[�X�͒n��A��邾�낤���B�^�X�ʐM�͉����G��Ă��Ȃ����A�A���Ă���Ƃ����������Ȃ�o�n�߂Ă���B���̐�����Ԃ͍��X�L�^����A�n��֑����Ă��邩��A�����s�K�ɂ��Đ����ċA��Ȃ��Ă��g�����h�ɂ͂Ȃ�Ȃ��킯�����A�����ċM�d�ȑ̌��������A���Ă�������ɉz�������Ƃ͂Ȃ��B�������ǂ�ȕ��@�Ől�H�q���Ȃ�������n��ɗU�����邩�͂ނ����������ł���ڂ��������m��Ȃ��҂Ƃ��Ă͔ޏ��̌��N�Ɩ������F��ق��ɂȂ��ł��낤�B�i�����j �i�ȉ����j ���������Ǖs�\ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�F�{�����V�� ���a�R�Q�N�i�P�X�T�V�N�j�P�P���S���i���j�[���@��ʁz |
���̈�ʂ̓X�v�[�g�j�N�Q���ł��グ�ɑ��锽�����A�O�ҎO�l�A��x�ɒ��߂邱�Ƃ��ł��Ėʔ����B����͐����I���_�A�Ȋw�҂̎��_�A�����ď����̎��_���B
�`���ł́u�Y���ꂽ�W���[�R�t�Ǖ��v�Ƃ��āA�O���ɔ��\���ꂽ�W���[�R�t�����Ǖ��̃V���b�N�����S�ɐ���������Ă��܂������Ƃ��`�����Ă���B�W���[�R�t�Ƃ͑���E���ɂ�����\�A�̉p�Y�ł���A���̎����h��b�B���̒Ǖ����O���ɕ��A�����͒��ݍ���ł����̂������i�⑫�P�Q�Ɓj�B���̋L���͋����ʐM�̎x�ǒ��ɂ����̂����A�ނ�̕��i�́g�K���h�Ƃ������i�H�j�A�����I���_�ł̊X�̔������I�m�ɑ������Ă���B
����A�i��ň��p�͗��������j�u�\�A�A�V�R�����g�p���v�Ƃ������o���ɖڂ��������B����ɂ��ƁA�ăX�~�\�j�A���V���䒷�̓C���^�r���[�ɑ��A�u���̋���Ȑl�H�q���ł��グ�����̗��ɂ́A���炩�̐V�^�R���̔���������̂ł͂Ȃ����v�Ƃ����������q�ׂ��Ƃ����B�Ȋw�҂̎��_�ł́A�������邱�ƂȂ���A���̃��P�b�g�̐��\���C�ɂȂ�Ƃ����Ƃ��낾�낤�B
�����Ă����ЂƂA�����̎��_���B����͌����܂ł��Ȃ��A���̑f��Ƃ��̉^���ɂ���B���̔����́u�F�����s���̃���������v�Ō����ɕ`�ʂ���Ă���̂œ��Ɍ����܂ł��Ȃ����A�܂����ڂ���Ƃ���A���̖��ɕ����̐������������ƁA�����Ă��̒��Ɂu�N�h�����t�J�v�̖����o�ꂵ�Ă��邱�Ƃł���B�����āu�X�v�[�g�j�N�v�A���̖��������ŏ��߂ēo�ꂷ��B�u�X�v�[�g�j�N�v�̓��V�A��ŒP�Ɂu�q���v���Ӗ����邾���̒P��ł���A�ŗL�����ł͂Ȃ������B�X�v�[�g�j�N�P���̑ł��グ��`����䂪���̐V���ł��A�u�X�v�[�g�j�N�v�Ƃ������t�͕\�ꂸ�A�u�l�H�q����P���v�ƋL���ꂽ�݂̂������i�u�X�v�[�g�j�N�̎v���o�v�Q�Ɓj�B�ܘ_�A�p��ł́uSputnik�v�Ƃ��ėp�����Ă��邪�A���{�̐V���Łu�X�v�[�g�j�N�v�Ƃ����P�ꂪ�o�������̂͂��ꂪ���߂Ăł��낤�B
�Ƃ���Łu���C�J�v�Ƃ������t�́A�\�A�̌������\�̒��Łg����h�Ƃ��ėp�����Ă�����̂ŁA���̊T�v����Z�ɐ�������Ă���B���������̌�A�u���C�J�v�����̌��̖��̂Ƃ��ėp������悤�ɂȂ��Ă��܂��̂́A�悭�m���Ă���Ƃ���ł���B
���̐��m�Ȗ��̂������ẮA���̌���\�A�͌������\���s���Ă��Ȃ��B���ǃ}�X�R�~�̓s���Ƃ��Ăǂꂩ�ɓ��ꂷ���ŁA���R�Ɂu���C�J�v�ւƎ��������̂��낤�ƕM�҂͎v���̂����c�B
���̉^���ł��邪�A�\�A���܂�̃t�����X�̉Ȋw�҃A���L�T���_�[�E�A�i�m�t���́u�\�A�͋A�҂�����Z�p�����ɏK�����Ă���̂ł͂Ȃ����v�Ƃ����������I���Ă���B���̑ł��グ�͐��������B�������A���Ă����̂��c���̌�A���Ԃ͂��̂P�_�Ő���オ���Ă����c�����ɂ͂��ꂪ�X�ɃG�X�J���[�g����B
��
| �@�@���͒n���ɋA���Ă���@�ʂ̗e��Ŕ��ˁ@�q���͉��Â��� �i���X�N���l�������C�^�[�A�����j���X�N���E�v���l�^���E�������p�W�G�L�����m�Ɠ����u�t�y�g���X�L�[�����͎l���A���C�^�[�L�҂ɑ��u�l�H�q����ɏ���Ă��錢�͓K���ȍ��x�ʼnq�����甭�˂����\��Œn��ɐ��҂���[���ȉ\���������Ă���v�ƌ��A����Ɂu���̐H�Ƃ͐�������ς�ł���v���Ƃ𖾂炩�ɂ����B �@�@�@�@�@�@�@�@  �@�@�{�^������ŒE�o ���k�b�v�|�@��A��q���ɏ���Ă��錢�������`�F�b�N�i�����ȃ������j�삪�F�����s�ɔ����e��̏����ɑ��Ď��������͑���킪�����A�e���r�ǂɂ���ċL�^����A���̏��͖����Œn��̊ϑ��҂ɓ`������B���̐S���̌ۓ��A�ċz�A�����A�����A�̉��Ȃǂ��L�^����Ă���A���̏��Ɋ�Â��ă��X�N���ɂ���Ȋw�҂̓{�^���������Č����q�����甭�˂��鎞�������߂邱�Ƃ��ł���B���̔��˂͋��炭�n���S�Ȃ����ܕS�}�C���i�O�S��\�`�Ȃ������S�`�j�̏��ōs���悤�B�q�����̂��̂͌�����ꂽ�e��̔��˂ʼne�������A���̌���������̋O������葱���邾�낤�B ��A�\���l���ɑł�������ꂽ��ꍆ�l�H�q���͓�̖ړI�A���Ȃ킿�����x�ł̋�C���x�𐳊m�ɑ��肷�邱�Ƃ���ё�C���O�̗����Q�ɂ��Ă̒m���邱�Ƃł������B�O���ɑł�������ꂽ��l�H�q���͐����ɂ��ẲF�����̉e���ɂ��Ă̒m���邱�ƂƁA�X�y�N�g���̌�����ړI�Ƃ������̂ł���B��q���̓X�y�N�g��������̐F�ɕ���������܃����Y�����Ă���B����ɂ��\�A�Ȋw�҂͋�C�ɂ���ĉe������Ă��Ȃ����z�����ڌ����ł��邱�ƂɂȂ�B�l�H�q������A���I�y�ђf���I�ɔ��M����Ă����̔��M�d�g�̑��ɂ����͒f�����̊Ԃɂ���G���̗ʂ���������̒m���Ă���B���Ƃ��Ήq���̓����̉��x�����܂�ΎG���͒Ⴍ�Ȃ�悤�ɂȂ��Ă���B ��A���͊ǂ�ʂ��ĉh�{�����������シ��B���̊ǂ͌��ɂƂ�����邪�A�����ɑ}������A���̊ǂ�ʂ��ăJ�����[�̍������������̓��ɑ��荞�܂��B ��A���̂���C�����ɂ͐��̃t���X�R��������Ă��邪�A���͂��炭�̊ԁA���Ȃ킿�����Ԉȏ�͏[���H�ׂ邱�Ƃ̂ł���H�Ƃ�^�����Ă���B�܂����P�b�g���̃e���r�ǂ͂��̌��̓��Â��L�^���A����𑗐M���Ă���B ��A���܂ōs��ꂽ�����ł͌������͓�S�`�̍����Ń��P�b�g����J�^�p���g�őł��o����A���҂��Ă���B���������͓�S�`����ꡂ��ɍ����ꏊ�Ŕ��˂���邩���m��Ȃ��B�����Ƃ������Ƃ��ẮA���̏����������v������P�b�g���O���̂����Ƃ��n�\�ɋ߂��_�ɂ����u�ԂɌ��˂���悤�w�͂���B ��A���͒n��ɋA���Ă��������炭�����Ă��邾�낤�B�����͌��҂��������Ɩ]��ł���B ��A������ꂽ�e��ɂ̓}�C�N���t�H���͓����Ă��Ȃ�����A���̐������Ƃ͂ł��Ȃ��B �i�ȉ����j �@�@���̐����L���b�`�@�č��̕����� �i�{�[�J�f���[���ăA�C�_�z�B���l�����`�o�A�����j�ăA�C�_�z�B�암�ɂ���j�a�k �h �����ǂ̃g���v�\���ǒ��͎l���A�\�A�̑�l�H�q���̔��M�d�g���猢���i���鐺�𑨂����Ǝ��̂悤�Ɍ�����B �{���ɂ���Ȃ������m��Ȃ����A�����ǂ̃e�[�v�E���R�[�_�[�͎O�����̂Ȃ������L�^�����B�ŏ����ق������ƁA���炭���Ă���l�x�����Ăق���̂������ꂽ�B�^�����ꂽ���̐��͂������ł��������A�L�����L�����Ƃ������ł͂Ȃ��A�����������̑����ق��鐺�̂悤�������B�l�H�q���̔��M�����L���b�`���ăe�[�v�E���R�[�_�[�ɋL�^�����͎̂O���̌ߑO�㎞�ܕ��i���{���ԓ����ߌ�\�ꎞ�ܕ��j�ŁA�����[���Đ������Ƃ��낻��܂ŋC�Â��Ȃ��������̂ق��鐺�������B �@�@�@������ԂM �i�����h���O�����`�o�C�����j�\�A�Ȋw�A�J�f�~�[�̃u���S�k���z�t�����͎O�����X�N��������ʂ���l�H�q���ɂ��Ď��̂悤�ɐ��������B �l�H�q���ɏ悹�������p�̌��g�������`�F�b�N�h�͖����ł���B��l�H�q���̊ϑ��҂͉q���́u�V���b�v�Ƃ������ɒ��ӂ��ꂽ�B���̉��͉Ȋw�҂ɈӖ��̂��邷�ׂĂ̎�����������A���̂悤�ȍ���ɑł�������ꂽ�ŏ��̐������ǂ̂悤�Ȋ��o���Ă��邩�𖾂炩�ɂ��鑽���̐M���������Ă���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�F�{�����V�� ���a�R�Q�N�i�P�X�T�V�N�j�P�P���T���i�j�����@��ʁz |
���X�N���̃v���l�^���E�������̔����́A���ꂪ�\�A���{�Ɍ��킳�ꂽ���̂Ȃ̂��ǂ������킩��Ȃ����A�����Ƃ��Ȃ肩������Ă���B�q���ɋA�ґ��u�͂Ȃ��������A�e���r�ǂ��������Ă��Ȃ������B�a�̂������A�`���[�u���A�̒��ɓ��ꂽ�����ł͂Ȃ��������A�C���J�v�Z���̒��Ƀt���X�R�Ȃǒu����Ă��Ȃ������B
�܂������ł͈��p���Ă��Ȃ����A�u���̓T����ł��グ�v�Ƃ����L���́A�v���E�_�����u���̉q���ɂ͉��l�ނ��悹���邾�낤�v�ƕ����Ƃ�`���Ă���B�v���E�_�̔��\�̓E�\�������킯�����A�������֒�����Ɉ�������Ă���B
���̐��Ɋւ��ẮA�}�C�N�͓��ڂ���Ă��Ȃ��������߁A��M���̂��̂����蓾�Ȃ������B�L�����̃g���v�\���ǒ��͂��̊��҂̈�S�ŁA���g�����h���Ă��܂����̂��낤�B���Ƀ}�C�N�����ڂ���Ă����Ƃ��Ă��A�ނ���M�����Ƃ������ԑтɂ͌��͎���ł����̂ł��������c�B
����ɂ��Ă��g�b�v�̌��o���u���͒n���ɋA���Ă���v���A�V���v���������͓I���B���̃C���X�g���X�A�����A���Ɍ��D���̕s���@���邩�̂悤�Ȋ�]�̌�������Ă���B
�Ƃ���ł���܂ł��o�Ă����u���S�k���z�t�́A�P�X�T�P�N�Ƀ\�A���n�߂����e����s�������ē��鍑�ƈψ���̈ψ����ł���A�ΊO�����̊�̈�l�������i�u�X�y�[�X�E�h�b�O�v���Q�Ɓj�B�T���̋L���ɂ��ƁA�ނ͌��̖����u�������`�F�b�N�v�Ɣ������Ă���B�����������ɋC�Â��̂́A�O���ނ́u�N�h�����t�J�v�Ɣ������Ă��邱�Ƃ��B���̂悤�Ȗ������A�}�X�R�~�ɐ��m�Ȗ��̂̓��������ɂ������\���͂��邾�낤�B��q�������A���ǃ}�X�R�~�́u���C�J�v�����̖��Ƃ��ėp������Ȃ������A�����́A�g���悤�ɂȂ��Ă��܂����A�ƌ�����B
���́g��h�u���S�k���z�t�́A�d�b�C���^�r���[�ɑ��A�傫�ȁg�����h�i�H�j����炩���Ă��܂��B����͉p���ł܂����A�䂪���ł��[���ŕ�ꂽ�B
| �@�@"���͂��̂܂��V"�@�\�A�Ȋw�҂������@�p���� �@�@�@�@�@�@�@�@  �M�Ғ��F�u���S�k���X���{�t���u���S�k���z�t �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�F�{�����V�� ���a�R�Q�N�i�P�X�T�V�N�j�P�P���T���i�j�[���@��ʁz |
�������ʂ��Ƃ������u���S�k���z�t�B���������̏ڍׂɊւ���₩��͓������B�ɂ����̂́A���̖����o�����O�ʼn������ꂽ���Ƃł���B�u�����͊O�o���v�Ƃ��������������E�\�Ƌ��Ɂc�B
���̌�A���V�A�v���L�O���P�P���V����ڑO�ɍT���A�u�V���Ɍ����A���Ă���̂ł͂Ȃ����v�u�����P�b�g��ł�������̂ł͂Ȃ����v�Ƃ��������������܂��Ă����B�����A���̐����Ɋւ���g�����̔��\�h�͉����Ȃ����炾�B�U���[���ɂ͂��ꂪ�[�I�ɏЉ��Ă���̂ň��p���Ă݂悤�B
| �@�@�Ԃ��r�b�N�����@�u�F�����v�̃S�A�҂��@���ւ䂭���P�b�g�� �����l�H�q���ł��グ�̐����͐��E�̖ڂ����X�N���ɏW�߁A���E�̎������X�N�������ɃN�M�t���ɂ����B�����̊v���l�\���N�L�O���ɂ́A��̉���ł�������̂��B���ւ̃��P�b�g���A�l�Ԃ��悹�����P�b�g���A����Ƃ��g���F���D�h���\���͐��E�e�n�ɗ�����ł���B�ȉ����̈�����������ƂƂ��ɁA���ܒn�����삯����Ă��郁�X�����������҂��邩�ǂ����Ƃ������P�b�g����̖��ɂ��X�|�b�g�����ĂĂ݂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �����Ɍ��ւ̃��P�b�g��ł�������Ƃ����E���T�͐^���ƂȂ낤���B���ւ̃��P�b�g�͂��\���A�����̋L�O���͂���������ł��\�ł���Ƃ������Ƃ̓\�A���͂��߁A���A�p�A�ĂȂǂ̐��Ƃ��������낦�đ��۔��������Ă���Ƃ��낾�B��������������ۂɑł������邱�Ƃɂ��Ă͈٘_���Ȃ��킯�łȂ��A�Ⴆ�A���H��̉��{�N�j�����́A���̑O�Ɉ�d�E���P�b�g��ł���������A����̂��̂ŁA�n���|���Ԃ̉F����ԏׂ���Ȃǂ��˂Ȃ�Ȃ����瓖���͂����������ƒf������B���������ɂ̓A�����J�̊w�҂̂悤�ɁA�����ɔ��\�ł���悤�ɁA���łɌ��ւ̃��P�b�g�͑ł��������Ă���Ƃ����Ă���l�����邱�Ƃ�����A�ǂ���ɂȂ邩�����ɂȂ�˂Ε�����Ȃ��̂��^�����B ���ւ̃��P�b�g�Ƃ��čl��������̂́A�l�i���P�b�g�ŁA���݂̂��̂��͈�i���������A�d�r�������Ƌ��͂Ȃ��̂��K�v�ŁA���̑���s�U�����u��ϑ����u�A�e���r�E�J�����Ȃǂ��܈ȏ�̌v��ނ��l�ߍ��ޕK�v�Ɖ���������邽�߂ǂ����Ă��ŏI�i�K����d�ȏ�̃��P�b�g�ƂȂ�B��Ȃ����O�d���P�b�g�܂ł͐����������h�b�a�l�i�嗤�Ԓe���e�j�Ƃ��āA�\�A�ł��łɎ����ς݂Ɠ`�����Ă��邩��A���P�b�g�̔R���A���͂Ƃ���������_����́A���͉����Ȃ��B���̓��P�b�g���I���������肷��A���Ȃ킿�܂��n���܂Ŗ߂��ď������ǂꂾ���ɂ��邩�A�]���ċO�����ǂ̂悤�ɂ��邩�A�n���E���E���z�̈��͂ȂǓV���w�I�e���ɂǂ��Ώ����邩�Ȃǂ̏��_�ɂ���B ���͒n�������O�\�����l��`����Ă��邪�A�A�����J�̃K���t���m��̌v�Z�����ɂ��ƁA�������O���ɂ��̃��P�b�g���̂��邽�߂ɂ́A���P�b�g�Ɏ����O�������S�l�\�`�ȏ�i���݂͎������甪�S�`�j�̏�����^���˂Ȃ�Ȃ��B���̑��x�͗e�Ղɏo���邪�A���̑��x���ƃ��P�b�g�̋O���͋ߒn�_�ɂ͕ς��Ȃ��A��������Ă��钷�~�O���Ƃ��邱�Ƃ��ł���B���̑��x�͂܂��n���̏d�͂���̒E�o���x�i������l�����Z�Z�`�j��������������K���n���֖߂��Ă���B���͌��̈��̖͂�肾�B �Ⴆ�Ό�����̋�������O���S�`�ɂȂ�ƃ��P�b�g�́A���̈��͂̂��߉�������A�n������̒E�o���x�āA��x�ƒn���ւ͖߂��Ă��Ȃ��B�܂����z�����P�b�g�̋O�������Ȃ�ς���͂������Ă���B���ւ̃��P�b�g�͂����́g�W�Q�h�͂��I����ɐ蔲���܂����p���āA�قڒn���ƌ��Ƃ~�̏œ_�Ƃ���悤�ȋO����`���āA�n���ɗ����߂��Ă��邱�Ƃ��K�v���B���̊Ԃ̏��v���Ԃ́A��̓�T�Ԃ���\���ł��邪�A�������Ė߂��Ă����g�����̎g�ҁh���P�b�g�́A�n��̂����ɐl�ނ̂����l�Ƃ��Č������Ƃ̂Ȃ����̗����̎p�⌎�̎���͂��߂����Ȍ������w��̋M�d�Ȓm���������炵�Ă����B �@�@�@�S���[�g���ɋ߂����@�l�Ԃ̂̂郍�P�b�g ���Ă��̌��ւ̃��P�b�g�́A�e���r�E�J�����Ȃnjv��͔����Ă��邪�A�l�͂܂�����Ă��Ȃ��B�������\�A�E�����o���̕��w�E����悤�ɁA�l�Ԃ���郍�P�b�g�̎������A�����������ɏオ���Ă���A�����̋L�O���ɂ��̔��˂����\�����\�����Ȃ��͂Ȃ��B���Ƀ\�A�̈�W�w�҂́A����ǂ̉q���ɂ͐l�Ԃ̎u��҂����������A�댯�������Č��ɂ����Əq�ׂĂ��邭�炢�ł���B�l�Ԃ��̂������P�b�g���d���̓_�ł͐l�Ԃƌ��Ɗi�i�̈Ⴂ�͂Ȃ�����A�l�H�q����Ƃقړ����d�����傫���Ȃ��Ă���d���炢�ł��ށB���͐l�Ԃ��Q�p�����Ƃ�˂Ȃ�Ȃ����߂ɁA�e�����P�b�g�̒��a���A���̏ꍇ�̔{�ȏ�A���Ȃ킿��E�܂Ȃ����O���[�g���܂ő傫������K�v�����邱�Ƃł���B �Q�p���ɂ���̂́A����ȊO�̒����Ȃǂ̎p���ł́A�����x���d�͂̎O�{�Ƃ��O�\�{�Ƃ��ɂȂ�ƁA�]�o����]�n�����N�����Ď��S���邩��ł���B�����̐Q�p�����Əd�͂̕S�{�܂ł̉����x�ɂ����C�ł���B�i�ȉ����j �@�@�@���x�͌��F���D�� ����͈�ԏ펯�I�����A��͂��ԉ\�����傫���B���������̌����P�b�g��̏ꍇ�́A��d���P�b�g�Ƃ��Ȃ�A������C�ł͂Ȃ����C�ƂȂ邩���m��Ȃ��B�ϑ��v��ނ́A���݂̌ܕS�`�]�̃��P�b�g�ŏ\�ƍl�����邩��A���������́A����]�v�悹���邱�ƂɂȂ�A�����P�b�g�ł͂Ȃ��āg���F���D�h�ƂȂ낤�B �@�@�@�����̔��\�g�~�X�E�F���h�̖������҂� ���������Ă���q�����̃��X�������҂��邩�ǂ����́A����̑����ł���A�������\�͂��ꂾ�Ƃ������Z�͑傫���B�i�ȉ����j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�F�{�����V�� ���a�R�Q�N�i�P�X�T�V�N�j�P�P���U���i���j�[���@��ʁz |
���N���N����悤�ȕ��͋C�̒��ɗ�Â���ۂ��A�l�X�ȉ�����������Ă���B�����P�b�g�����̒��ŁA�O���Ɋւ��鉯���͒��ڂɒl����B��ɂ����n�ōs���悤�Ȋi�D�Ŏ������邩�炾�c�P�X�T�X�N�P�O���̃��i�R���ł���B
���Č��ǁA�V���Ƀ��P�b�g���ł��������邱�Ƃ͂Ȃ������B���̓��n�܂����\�A�ō���c�Ńt���V�`���t�͉������A�l�H�q�����č��ɐ�s���Ă���Ƃ������Ƃ��ւ�A�x��C���̍H�Ɛ��Y���P�T�N�ȓ��ɒǂ��z���Ɛ錾�B�v���S�O���N�̐ߖڂɂ�����A���̎Љ��`��������]���}�������ōs��ꂽ�����͂R���ԂP�O���ɒB�������A�������A�d��Ȕ����͂Ȃ������B
��
�P�P���P�O���A���X�N�������̓X�v�[�g�j�N�Q������̃f�[�^���M����~�������Ƃ����\�����B���̒��ŁA�ړI�Ƃ��Ă����f�[�^���W�͊��S�ɍs���A���M�͗\��ʂ��~�������Ƃ��q�ׂĂ��邪�A���̐����ɂ͈�ؐG��Ȃ������B
����A�C�^���A�̋��Y�}�@�֎��u���j�^�v���A�u���C�J�͎��v�Ƃ������o���L���ŁA���X�N�������̕�`���Ă���B���������y���̂��߂ɓŎE���ꂽ�ƕĂ���̂����A���̏�͂͂����肵�Ă��Ȃ��B���̕ӂ́A���j�^���̉����L���ł���\���������i���̌��ɂ��Ắu�`���̌��E���C�J�v���Q�Ɓj�B
| �@�@�q���̔C���I���@���S�Ɏ��������@���M�͗\��ʂ�Ƃ܂� �@�@�@�@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�F�{�����V�� ���a�R�Q�N�i�P�X�T�V�N�j�P�P���P�P���i���j�[���@��ʁz |
����ƍ��킹�ďЉ��Ă���A��A�̃\�A�q�������ɑ���č��l�̐��_���͂��ʔ����B����͑傫���A�u���Ȕᔻ�^�v�A�u�����ɂ��^�v�A�u�ق����Ԃ�^�v�̂R�ɕ�������Ƃ����B���Ȕᔻ�^�́u�撣���Ăł��邾�������\�A�ɒǂ������v�Ƃ��������A�����ɂ��^�́u�l�H�q���͐����������ǁA���S�͖̂��J�������ł͂Ȃ����v�Ƃ��������A�ق����Ԃ�^�́u�����ăX�v�[�g�j�N�̘b��ɐG��Ȃ��ԓx�v�ł���Ƃ����B
���̂悤�ȃX�v�[�g�j�N�֘A�̋L�����A�قږ��������Ă����B�P�R���ɂ̓^�X�ʐM���J�v�Z���ɓ��������C�J���B�e�����L���Ȏʐ^��q���S�̂̎ʐ^�����J���A���ꂪ�P�S���̒����Ɍf�ڂ���Ă���B�܂��A�P�R���A�v���E�_���͓�ʂƎO�ʑS�̂��g���ăX�v�[�g�j�N�Q���̏ڍׂ�����A����ɐG�ꂽ�L�����P�S���̗[���ɋL�ڂ���Ă���B
�v���E�_���́̕A��ɏオ�����X�v�[�g�j�N�P���̎������R�����ł���Ƃ������Ƃ�\�����Ă��邪�A�P���̃~�b�V�������Ԃɂ��ĐG���ꂽ�̂͂��ꂪ���߂āB�܂��A�X�v�[�g�j�N�P���̖͌^���P�Q���A���X�N���̎Y�ƓW�œW�����ꂽ���Ƃ��ʐ^�t���Ō��J���Ă��邪�A���ꂪ�P���̐��E�����J�ł���B���������̓W����ł́A�Q���̖͌^�͓W������Ȃ������B
�Ȃ��A�u���͐������܂ܒn��ɋA���Ă������A�R����̗��R���炻�ꂪ�������Ă���̂ł͂Ȃ����v�Ƃ��������͑��ς�炸�����Ԃ葱���Ă���B
�^�X�d��X�N�������Ƃ������\�A���{�̐����̌`�ł̃��C�J�̎��́A���Ǔ`�����Ȃ������B����Ɍ���A�\�A�Ȋw�A�J�f�~�[�̉�̐ȏ�A����͖������ꂽ�B
| �@�@"�F����"�̎��\�@�u�~���H�v�Ȃ������v�@�炻���Ƀ\�A�Ȋw�� �i���X�N���\�ܓ����苤�����h���j���E�̒��ڂ��W�߂Ă���l�H�q�����ɂ��Č��Ђ̂����^����\�A�Ȋw�A�J�f�~�[����Ƃ̋L�҉���\�ܓ��ߌ���i���{���Ԍߌ㔪�����j���烂�X�N���̕����A���ψ���̉���ōs��ꂽ�B�������Ȃ����̋L�Ғc�����̓�����͑������Ŗ�S�\�l�̓��O�L�҂��߂����A�A�J�f�~�[���̒n���ϑ��N�ψ����o���W�����m�玵���ɂ��ϑ��N�i�s�̐����ɑ����Ė�ꎞ�Ԃɂ킽�莿�^�������s�����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ 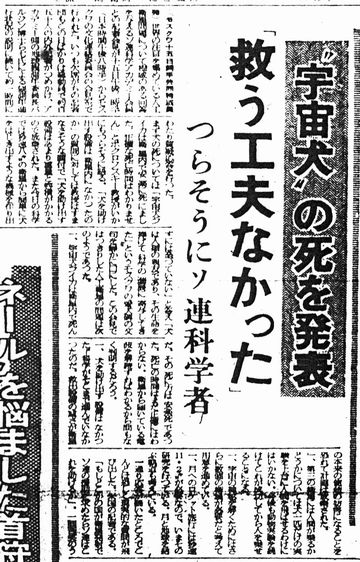 �܂����̎��ɂ��Ắu�F�������C�J�͉q�����ň��y�Ɏ��ɂ܂����B���m�Ȏ��S�����͂킩��܂���v�ƃ{�N���t�X�L�[�����������ɂ��炻���Ɍ��B�u���������o���ݔ��͉q�����ɂȂ������̂��v�̎���ɑ��Ă͋����͂��܂Ȃ������Ȋ�t���Łu���������o���ݔ��͂��܂�d�ʂƗe�ς�������̂ŕ������ꂽ�B�܂������̉Ȋw�ł͕b�����`�̉q������ȒP�Ɍ����͂����o���悤�ȋ@�B�����o���ɂ͎����Ă��Ȃ��v�Ɠ����u���͐l�ނ̐e�F�ł���A���̐���������ĉȊw�̐i�W�Ɋ�^���Ă����v�Ƃ������X�N���́�����̕����Â��Ɍ��ɂ����B���̉�ł͂����肵���l�H�q���̖��͎��̂悤�ł������B ��A�F�������C�J�͉q�����Ŏ��B���̎��ɕ��͈��y���ł������B���S�̎��Ԃ͂܂����m�ɂ͂킩��Ȃ��B�q������͂��Ă���d�g����ǂ���킩�邩��Ԃ��Ȃ��������邾�낤�B ��A���������o���ݔ��͂Ȃ������B�Ȋw�������܂Ői��ł��Ȃ������̂��B�~�o�ݔ��̏d�����q���̖{���̎g���̖W�Q�ɂȂ邱�Ƃ�����Čv��͔j�����ꂽ�B ��A��O�̉q���ɂ͐l�Ԃ���邩�ǂ����ɂ��Ă͌���C�����̎�����y��ɐl�Ԃ����킯�ɂ͂����Ȃ��B��������������𑱂��Ă��ꂪ�������Ă���l���悹�邱�ƂɂȂ�B ��A�F���̐_����������߂ɂ͂���ɐ��̉q�����K�v���ƍl���ėp�ӂ�i�߂Ă���B ��A���ւ̃��P�b�g���s�ɂ͕b���P�P�E�Q�`���K�v�Ȃ̂ŁA���܂��̌������s���Ă���B���ƒn�������ԋO�����l���Ă���B ��ʂ�̉������������Ƃ���ł���ǂ͋��낵�������I�Ȏ��₪��яo�����B�č��̋L�҂ł���B�u�����ǂ����̍����q�����˂Ń\�A�̉��������߂���\�A�͂���������邩�v�B��u��̂����Ƀo���W���ψ����́u�Ȋw��̉����͂��Ƃ��ɂ��݂܂���B������]�̍�����������\���o�Ă��������v�Ɠ������B���ꂩ��b�͂܂��������ɕԂ�A ��A�ꍆ�Ɠ̔R���͑S�R�������̂ł������B���˂̏ꏊ���ǂ��ł��������͉Ȋw��̋����͂Ȃ��B���X�N���ł����Ă����V���g���ł����Ă��������Ƃ��B ��A�\�A�ł͐l�H�q�����w�����Ă���͉̂Ȋw�A�J�f�~�[���B����ȊO�̗Ⴆ�ΌR�����W���Ă��邩�ǂ����ɂ��Ă͓����Ȃ��B ��A��O�̉q�������オ�邩�A����ɂ͂ǂ�ȓ�������邩�A���̓_�͑�O���q�����̂��̂̌v�悪���肾����Ȃ�Ƃ������Ȃ��B �Ȃǂ����炩�ɂ��ꂽ�B�Ō�ɓd���w�̃p�N�[�j���������ꍆ�q����ʂ��Ă̌����ɂ������Đ��E�̃n����������M�d�ȉ��������A�e�����h����ʂ��Č���\�������Ɩ�\�l�̖��O�����������A���̒��ɂ͓��{�l�A�}�`���A�����ƃi�J�j�V�G�L�q���̖��O������ꂽ�B ���������Ǖs�\�B�u���v���u���v���H �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�F�{�����V�� ���a�R�Q�N�i�P�X�T�V�N�j�P�P���P�U���i�y�j�[���@��ʁz |
���̖��ɂ��ă\�A�����u�F�������C�J�v�ƌ����Ă��邱�Ƃ���A���C�J�����̂܂܌��̖��ɂ��悤�Ƃ������Ƃ��킩��B�������u���C�J�v�łقڒ蒅�������̐����ԂŁA�\�A��������ɍ��킹�����H���邢�͂��͂�A�ǂ��ł��悭�Ȃ������H�܂��A�����ǂ̎��_�Ŏ��̂��킩��Ȃ��Ɛ����ɓ����Ă������A���y���Ƃ����̂̓E�\�ł͂Ȃ����c����̃C�^���A���́A�o���s���̕��t�ɂ��̂܂ܗ��p�����̂ł͂Ȃ����ƕM�҂͍l����B
�܂��A�ꍆ�Ɠ͓����R����p���Ă���Ƃ������Ƃ��������Ă���Ƃ���́A���P�b�g�ւ̊S�̍����ɑ���ԓ��ƌ�����B���Ȃ݂ɂh�b�a�l�Ɖq���ł��グ���P�b�g���������̂ł���Ƃ������Ƃ̌������\�͂Ȃ��������A�P�O���P�X���̎��_�Ń\�A�̉Ȋw�҂��������̂ł���ƃC���^�r���[�ɓ����Ă���B
��̋L�����������L�҂́A�u���̎��S�̎��Ԃ́A�Ԃ��Ȃ��������邾�낤�v�Ɗy�ϓI�ł���B���������́g�Ԃ��Ȃ��h���A�S�T�N�Ԃ��������ƂɂȂ�Ƃ́c�B�i�ڍׂ́u�`���̌��E���C�J�v���Q�Ɓj
��
�\�A���ł��������Q�̉q�����c�������̂́A���������̂ł��낤���B���ꂪ�ꌾ�Łu���ꂾ�v�ƌ����邱�Ƃ̂ł��Ȃ����̂ł���̂͊ԈႢ�Ȃ����A�ڂŌ��Ă킩��₷�����̂��ЂƂ������B
����́A�F���ւ̊S���L���@��N�������Ƃ������Ƃł���B�P�����ł�������ꂽ�P�O���ȍ~�A�܂���̒n���ϑ��N�̎�������A�����̉F���ւ̊S�͐���オ��A�Q���̑ł��グ�ł���͍ō������}����B�l�X�͖{���֎E�����V���֘A�̏��������߁A�f�p�[�g�ł͌����Ĉ����͂Ȃ��V�̖]����������ɔ���܂���A�v���l�^���E���͑吷���A�������ɉΐ��̓y�n���w������Ƃ������l���������o����قǂł������B�ȉ��A�������L���̈ꕔ�߂Ă݂悤�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�F�{�����V�� ���a�R�Q�N�i�P�X�T�V�N�j�P�P���W���i���j�����@�V�ʁz �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�F�{�����V�� ���a�R�Q�N�i�P�X�T�V�N�j�P�P���P�V���i���j�����@�R�ʁz |
�����A����́u���v�ł������B���������q���Ɍ��炸�A�Ȋw�����E�j�b�|���̑ٓ���`����b��͂�������イ���Ă����̂ł���B���̔N�����Ō����Ă��A�傫�Ȃ��̂͗Ⴆ�Γ�Ɋϑ��D�̏o�q�A�䂪�����̌��q�F�i�����p�j�̉ғ��Ȃǁc�ڂ̑O�͕n�����Ƃ��A�P���������茳�Ɋ�G���W�j�A��Ȋw�҂̓q�[���[�ł������B�����Ă��̋��ɂ��A�q���ł������Ƃ������Ƃ������邾�낤�B
�䂪���̃��P�b�g�J�������͂ɐ��i�������싳�����p�ɂɃC���^�r���[�ɓ����A�����A�����č������ׂ������̍�����A�M������Ă����̂ł���B
| �@�@"�l�H�q��"���̃X�e�b�v�@���g���P�b�g�͂܂�"��"�@���싳���ɍ\�z�� �@ 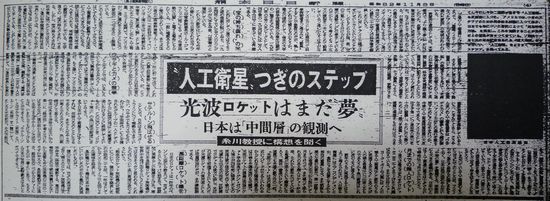 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�F�{�����V�� ���a�R�Q�N�i�P�X�T�V�N�j�P�P���W���i���j�����@�S�ʁz |
���⑫�P
�W���[�R�t�i�Q�I���M�[�E�R���X�^���`�m�r�b�`�E�W���[�R�t�j�͗��̌R�l�ŁA����E���i���V�A�ł́g��c���푈�h�j�ł̓x�������ח����̃\�A�R�i�ߊ��Ƃ��Ēm���Ă���B�ȒP�Ɍ����g�\�A�̃A�C�[���n���[�h�ł���A�\�A�������ɓ������p�Y�Ƃ��ē��O�ō����]���Ɛl�C���Ă����l���ł������B
���A�t���V�`���t�h�Ƃ��ăX�^�[�����h�̒ǂ����Ƃ��Ɉ���A�}�̗v�E����C�������A�܂��܂����܂邻�̐l�]�ƌ��͂̓t���V�`���t�̖ڂ̏�̂��ԂƂȂ����B�t���V�`���t�̏���R�팸�Ăɔ����������Ƃ��Η���[�߂錋�ʂɂȂ����Ƃ����B
�W���[�R�t�͂P�O���A���[�S�X���r�A�E�A���o�j�A�����̖K��ɏo�����A���Q�U���ɋA���������A���̓����A�ނ̉�C�����\���ꂽ�B���̍��W���[�R�t�ƃt���V�`���t�̊W���₦�Ă��邱�Ƃ͐����ł����m���������A����͑S���̔����ł��ŁA�����ɂ͂��̐^�����S�R���߂Ȃ������B�\�A�s���������̃V���b�N�ɑł��f���ꂽ�Ƃ����B
�����A�����́̕A����͎��i�ւ̏����ł͂Ȃ����Ɗϑ��������A���̌�̓��Â��S�����߂Ȃ����ƁA�����������[�S�E�A���o�j�A����̋A���̍ہA��`�ɗv�l���N���o�}���ɏo�Ă��Ȃ��������ƂȂǂ���A�Ǖ����ꂽ���̂Ƃ̌��������܂��Ă����B
���ǂ��̐^�����͂����肵���̂̓X�v�[�g�j�N�Q���ł��グ�O���̂P�P���R���ł���A���h����C�݂̂Ȃ炸�A�����̒����ł������\�A���Y�}�����ς���̊��S�Ǖ��������ɔ��\���ꂽ�B���R�́u�}�̌��Ђ݂ɂ������v�Ƃ������Ƃł������B����܂��傫����ꂽ���A������X�v�[�g�j�N�Q�������S�ɏ����������Ƃ����킯�ł���B
| �@�@�W���[�R�t���h����C�@��C�}���m�t�X�L�[�����@ �@�@�@�@�@ �@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�F�{�����V�� ���a�R�Q�N�i�P�X�T�V�N�j�P�O���Q�V���i���j�[���@��ʁz |
���r�������Ƃ܂���A�A�C�[���n���[�Ƃ������}�b�J�[�T�[�̂ق����Ó����낤���B�������P�X�U�S�N�P�O���A�t���V�`���t�̎��r�ɔ����A�W���[�R�t�̖��_�͉���Ă���B
�yReference�z�ǂ̎������ڂ����킩��₷���A���E�ł��I
�F�{�����V���i�ڍׂ͊e�L�����Ƃɖ��L�j